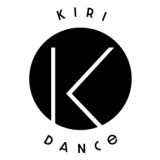――目の前のそれが現実だと、誰が証明できるだろう?
――誰も彼もが蜃気楼の中にいるような世界で、真実に価値なんてあるのか。
と、カメラマンの長谷部京輔は常に感じている。
彼はフリーのカメラマン兼ライターのようなもので、いくつかの雑誌に連載の枠を貰っていて、大儲けというほどではないが困窮するほどでもない生活を送っている。依頼があればそつなくこなし、特集に沿った記事を書く。特にこの仕事にこだわりがあるわけでもなく、辞めたくなるほど嫌悪もしていない。色々な意味で“普通”の人間だ。少なくとも彼自身はそう思っている。
その日は長期出張の初日だった。長谷部が今回引き受けた仕事は、普段の連載記事とはまた毛色が違っていて、まず非常に報酬が多い。更に内容は本格派を謳っていて、腰を据えて撮影なり取材なりをしなければ間違いなく先方から突き返されるだろう。引き受けた手前半端な仕事ができるはずもなく、こうして現地に宿を借り、1ヶ月ほど滞在することになった。
都心から特急電車で2時間ほどのその土地は、一言で言うならば田舎だろう。連なった背の低い山々のちょうど凹んだ部分に、ぽっかりと集落ができている。そうは言ってもスーパーやガソリンスタンド、ちょっとした娯楽施設などはあるため、都会の喧騒に嫌気が差した人間などはよく越してくるようだ。畑が点在する住宅地には比較的新しい一軒家が見え、人口もさして少なすぎるほどでもない。長谷部の第一印象で言えば、「中途半端」だった。この土地での目標は、戦場跡にある。過去――500年ほど前だっただろうか――にこの付近では多くの血が流されたと言う。その際に生じた歴史的遺物がこの土地に遺されているらしく、長谷部自ら撮影及び取材にやって来た。“中途半端”であるためか、それとも立地のせいか、インターネットでもあまり情報を探すことができず、なんとか人伝でここにたどり着いたくらいには穴場のスポットである。まだ世に知られていない場所は、容易に新規性が手に入る。
しかし――
「あつい……」
思わず長谷部は独りごちた。彼は今、とにかく土地勘を掴もうと散策に駆り出している最中であるが、何分今は7月であり気温は30度を越している。更に宿に到着してすぐ飛び出してしまったため、時刻は正午をすこし過ぎた辺りだ。盆地特有の湿気が不快感を増幅させ、ダメ押しのように周囲には低い民家ばかりが並ぶため、暑さを避ける日陰もない。三十路を過ぎた人間の体力では早々に限界が来そうなものだが、宿に戻るよりはどこかの店にたどり着くまで歩いたほうがいいかもしれない……とぐだぐだしている間に、戻るに戻れなくなっていた。道中の自動販売機で購入したスポーツドリンクはとっくに温まりきっている。
「にゃあ」
そんな長谷部の状況にはいっそ不釣り合いかつ場違いなほど、涼やかな声が耳に滑り込んできた。声の主を追って顔を上げると、右手側頭上――道を形作るブロック塀の上、生い茂る木々の木漏れ日に隠れて、ぶちまだらの猫がこちらを見ていた。茶と黒でまるで汚れたような模様をしているそれを見ながら、長谷部がサビと言うんだったか……などとぼんやり考えていると、猫はふたたび「みゃあ」と鳴いて歩き出した。猫は気ままに軽やかに、この暑さなど問題ではないように歩いていたので、長谷部もなんとなくその猫を追いかけてみた。気分だけでも暑さが和らげば良い。
並んでいた民家がぽつぽつと減っていき、ついには見えなくなり、舗装された道と木々だけが視界を埋め尽くした。一体どこまで来たんだ、と長谷部は帰り道を案じてため息をつきたくなるが、猫はずっと歩き続けている。まるで道案内をしているような猫は、やがて歩みを止めた。しかし長谷部は猫の方をすでに見てはいなかった。目の前に、ぽつんと佇む古い建物を認めたからだ。
それは中央にガラス張りの引き戸がついた、昔ながらの木造家屋だった。引き戸の前には簡素に「開店中」とだけ書かれた木の板が立てかけられているため、辛うじてなんらかの店であることがわかる。しかし看板も何も掲げられていないのでなんの店かはわからない。ガラス戸から中を覗き見ようとしても、背後から強い日光が差し込む状態では、少し薄暗い店内の様子を知ることはできない。何もかも謎に包まれた店構えではあったが、不思議とその店はもの場所に馴染んでいた。というより、違和感を覚えない。こんなに唐突に、町のはずれに、一軒だけぽつんと建っているというのに、もしこの店の前を車で通り過ぎても、きっと気づかないだろうなと長谷部は感じた。それほどにこの道の空気に溶け込みすぎている。
なんの店かは謎であるにせよ、長谷部は長い時間炎天下を歩いてほとほとに参ってしまったため、躊躇いなく店の戸を開けた。なんとか上手いこと店主に休ませてもらおうという魂胆だ。幸いそこそこに取材の経験はあるため、他人の懐に入る技量に不安はない。とにかく疲れていた。
「すいませー……ん……」
店の中に向けて投げかけた声が、段々と尻すぼみになっていく。
店内の壁は作りつけられたシンプルな棚が埋めていて、そこに茶器やら皿やらが無数に並んでいる。同じように中央にも陶器が置かれた大きな棚が3つほど並んでいて、どれも状態はいいが少しの傷や染み付いた跡があるため、ここが古物店だとわかった。整然と――いや、むしろ素っ気なく並べられた棚の他には装飾らしい装飾もなく、剥き出しの梁や柱が更にその印象を加速させる。店内はほんのりと薄暗い上、木々に周囲を囲まれているためか、この場所自体がぽっかりと空いた“日陰”のようだった。実際に店内は冷房をつけている風ではないのに快適な気温になっていて、なんとなく先ほどの猫が好みそうな立地だな、と思った。居心地に関してはいっそ不自然なほどに馴染む店だったが、問題は人の気配がしないことだ。あらゆる箇所に店主の人間味が見えてこないし、そもそも店内に人がいるか怪しい。看板が立ててあったから開店中であることに間違いはないのだろうが――
(留守か? 田舎じゃ店開けたまんま留守にするのも珍しいことじゃないが……)
人のいない店内に長居するのは正直あまり気が進まない。しかし、未だにギラギラ照りつける太陽と、体に蓄積された疲労と、渇ききった喉が外に出るのを全力で拒み続ける。
(まあ、せっかくだし商品を物色するか)
などと心の中で言い訳をつけて、結局居座ることに決めたとき、“それ”は突然に現れた。
「……いらっしゃい」
いや、おそらく“それ”は突然現れたのではなかった。元々この狭い店内にいたはずだ。いたはずなのだが、存在感をまったく感じられなかった。まるで“それ”が認識することを許したから見えるようになったような、そんな唐突さだったから、突然現れたように思ったのだ。
“それ”は男だった。中途半端に長い髪と、片目を覆い隠すほど長い前髪、中性的な顔立ちや体つきだけでは性別の判定すら難しいが、かけられた声の低さと、纏った男物の着物がそれを表していた。男はゆったりと和服を着流して、肩には羽織をかけている。年齢の印象はまったく曖昧で、若いようにも、老成しているようにも見えるため、和服が似合っているか似合っていないかも測りかねる。伏せ気味の瞼や色の薄い表情から、かなり陰気に見えてしまって、全体的に印象が定まらない人物だ。なんとなく、この建物の主にぴったりだという気持ちになる。
長谷部は一瞬驚いて固まってしまったが、我に返ると手に取っていた皿を棚に戻し、男に向き直った。
「あ……こ、これはどうも、気づきませんで。 店主の方ですか?」
「ああ……」
「そうでしたか。良いお店ですね、隠れ家って感じで――」
「売り物を見に来たわけではないんだろう? ……そこに座って、少し待っていろ……」
印象通りに素っ気なく言って、店主は目線だけで隅の小さい丸椅子を指した。そして返事も待たぬまま踵を返すと、店の奥に引っ込んでしまう。歩いた先には勝手口のような戸がついていて、おそらく更に奥の居住スペースが存在するのだろう。
長谷部は戸の向こうに消えていく背を見送ると、素直に指示された丸椅子へ腰を落ち着けた。どうやら仲良くなって快く休ませてもらおう、という作戦は不要だったらしい。店主は長谷部の魂胆をわかりきった上で、嫌そうにするではなく、しかし歓迎するでもなく、何やら飲み物でも持ってきてくれるらしい。長年店をやってくれば商品目当てではない客も区別がつく、ということだろうか。
(いや、それにしては――)
どこか心の中でも見透かされているような、そんな目だった。しかしそれは長谷部にとって不快なものとは思えなかった。
ぼんやりと天井の梁を見つめていると、目の前に湯呑みが差し出された。少し視線を上げれば、差し出した本人がこれまた読めない表情で漫然と長谷部を見ている。会釈と軽い謝辞を述べて湯呑みを受け取った。中身はどうやら冷たい緑茶のようで、ご丁寧に氷まで浮かんでいるのに、それを入れているのがガラスのコップでなく湯呑みというのが、なんとも不釣り合いで少し笑ってしまった。こういうところは雑なんだな。
「助かったよ。道中に店らしい店もなかったもんだから」
一気に半分ほどを煽って一息つき、長谷部はそう切り出した。完全に敬語ではなくなっているが、この店主には不要だろうという長谷部の判断だ。
店主は向かいに同じような丸椅子を置いて腰掛けている。彼もまた湯呑みを手にしているが、中身は熱い緑茶のようだ。この暑いのに奇特な奴だな、と長谷部は思ったが、彼らしい、ともまた感じている。会ったばかりだというのに他人行儀な空気をなくさせてしまう、妙な雰囲気が漂っていた。
「そうだろうな――この辺りは、人通りも少ない……力尽きれば、生きて帰るのも難しかったかも……しれない……」
なにやら物騒なことを呟いて、店主は手元の湯呑みを一口啜る。長谷部は絶句して若干血の気が引いたが、気を取り直して店主を観察する。
彼は呟くように言葉を紡ぐ。簡単に言ってしまえば声が小さい。口の中だけでボソボソと喋るため非常に声がこもっているのだが、不思議と長谷部は聞き取れないということはなかった。それはこの店が静寂に包まれているからかもしれないし、店主の声が何故だか耳障り良く聞こえるからかもしれない。前髪から除く伏せがちな目は滅多に長谷部の方を見ないが、見たら見たで、どこを見ているのかよくわからない瞳をしていた。長谷部の内部を見透かしているような、むしろどこか遠くを見ているような、その視線は居心地が良かった。長谷部は仕事の都合上、他人と話す機会が多くある。人間は他人を見るとき、他人を見ながらそこに自己をすべり込ませる。内在させた自己をこねて固めて、やっと“他人”を理解した気になっている。そういうものだと長谷部は感じている。だからこそ、他人にまるで自己を映さない、鏡のようにガラスのように映し返す店主の瞳は、新鮮であり懐かしかった。
「あんたは何故こんなとこで店を?」
「さあ……どうだろうな。この場所に理由があるわけではない――ああ」
長谷部の世間話に相変わらずボソボソと返した店主は、思いついたようにガラス戸を通して外を見るように顔を上げた。
「ロキが……ここを気に入っていたから、かもしれないな」
「ロキ?」
「君を連れてきた猫、だ」
その様子を見ていたのか、とか、猫をまるで案内屋みたいに言うんだな、とか、長谷部は色々思うことはあったが、少しだけ悪戯っぽく笑った店主に驚いて口を噤んでしまった。反射的に力んでしまった手で湯呑みが震えて、中の氷がからりと音を立てた。そこでやっと緑茶の存在を思い出して、誤魔化すように一口飲み下した。十分に潤った口を開いてまた問いかける。
「古物屋は好きでやってるのか?」
「随分と質問が多いな……」
「雑誌記者みたいなもんでね。インタビューが癖になってるのさ」
「……仕事熱心だな。店、か……」
そこで店主は、薄暗い店内をぼんやりと見る。それは商品や店内を見つめているというよりは、その先にある何か、得体の知れない何かを視ているようで、今度は落ち着かない気分になった。
「正しいとはなんだと思う?」
唐突に、店主は長谷部に語りかけてきた。長谷部の質問の途中だったので戸惑いはしたが、店主があまりにも空気に馴染んだ問いかけをするものだから、長谷部は己の質問を忘れて、店主の問いに頭を働かせた。
「正しい、って……正義ってことか? 法とか、規則みたいな」
「法や規則は人間が生きるための“型”に過ぎない……その型は時と状況によって容易に姿を変え……時に、信じていた者さえも、裏切ることがある……。それを正しい、と思うか……?」
「いいや、思わないな。じゃあなんだろうな。形のあるもの、とか、目の前にあるもの、とか」
「形あるもの、目の前にあるもの――果たしてそこにどんな価値がある? 君の見ている世界は、すべて虚構かもしれないのに、だ」
「…………」
「世界は、君が思うよりもずっと脆い……遥かに不安定で、誰にもそれを確立することはできない。ならば一体どこに、確かなものが存在するか……」
「……人間の中、か?」
「そうだ。法も規則も、そして世界さえも、決して確実ではない。しかし……己の、その意思ならば、己が存在する限り――保ち続けることができる。たとえそれが、不安定な世界との間にのみ存在し得るものだとしても、己が信じる限りは、それを“正しい”とすることができる……」
店主は突然饒舌に語り始めた。およそ演説とは言えないほど声に張りがなく、自信に満ち溢れているわけでもなく、相変わらず視線は虚空を向いていたが、言葉には奇妙な確信を持たせる力があった。少なくとも長谷部は彼の言葉をいつの間にか前のめりに聞いていたし、更にこの言葉を引き出したい、と感じている。
「それで、その“正しい”が、どう店に関係するんだ?」
「誰かの手に一度渡ったものは、その誰かの“正しさ”が付随する……自分にとってなんらかの価値があると認めて購入し、少なからず価値があると考えて売却する。それは、“価値”という不確定な要素に支えられたものだが、同時に……人間の中で揺るがない、確固たる意思を背負っている。蜃気楼のように移ろうからこそ、視えるものもある――だから、この店をやっている」
店主はいつの間にか傍らの棚から小さい白磁器のカップを手に取って、指先で弄んでいた。長谷部はというと、店主の掴みどころのない話に首を捻りながら、しかし妙な納得を覚えていた。彼の考える意味の半分も理解できた気がしないが、同時にそれで良いとも考えている。店主の考えていることを“理解しようとしない”ことが、今の自分にとって最も正しいと思える行動だった。長谷部はまた湯呑みに口を付けて、「そいつはすごいな」と軽い調子で嘯いた。
「古物は特に、先の未来が視えやすい。……どういった人生にしたいか、というような相談にも……乗ることができるな……」
「なんだそりゃ。占いや風水までやってるのか」
「まあ、そんなようなものだ」
今度は明らかに適当に流したような口調で、店主が薄く笑みを浮かべる。長谷部もなんとなくしてやったりな顔を浮かべて、残った緑茶を飲み干した。店主は長谷部の手から空になった湯呑みを受け取ると、立ち上がって奥に引っ込もうと歩き出す。その背中に長谷部は少し声を張って話しかける。
「なあ」
「……なんだ」
「おかわりくれよ」
半分だけ振り返った横顔に見える右目がほんの僅かに見開いたのを確認して、長谷部は更に笑みを深めた。店主は呼吸と見分けがつかないようなため息を一つだけ吐いて、完全に長谷部へ向き直って苦笑を浮かべる。
「……図々しい客人だ」
そして再び奥へと去っていった。長谷部はというと、変わらず丸椅子に腰掛けたまま、店主の帰りを待っている。“おかわり”を持ってくるのを微塵も疑っていない様子だった。彼は一人でいる間もずっと笑みが抑えられず、かといって収めようともせず、にまにまと緩む口元をそのままにしている。
(こんなに楽しいの、久しぶりだな)
子供のように躍る心と裏腹に、店内の静謐な空気と混ざり合うように理性は凪いでいて、まるで瞑想をしているようにじっと座っていた。そして目の前にはなみなみと緑茶の注がれた湯呑みが差し出されて、軽やかで厳かに、それを受け取ったのだった。
「俺は長谷部京輔。あんたは?」
「柊――いや……ハリウッド、か」
「変わった名前だな。よろしくな、ハリウッド」
◇◆◇
それからの長谷部は、日課のように足繁く柊の元へ通った。午前と昼は取材と撮影をして回り、一段落ついて街から人気がなくなった頃、いそいそと街外れの古物店に向かう。初めて出会った日から自然体の二人だったが、翌日以降も変わらず居心地の良い時間を過ごした。長谷部が当然のように店に顔を出すので、柊も当然のように迎え入れて、湯呑みに入れた冷たい緑茶を用意する。時折、長谷部が手土産と称して軽い菓子を持参することもあった。二人の話は取り留めもないものだったが、それゆえ長谷部は仕事のことを忘れて、体も心も休めることができた。柊の様子は相変わらずの冷静さ――というには些か素っ気ないもので、長谷部としては自分がどう思われているのか測りかねた。しかし、柊が訪問を拒んだことはなかったために、少なくとも憎からず思われているのだろうと結論づけている。それに、柊の前では、目の前の自分が好きか嫌いかなんて瑣末なことだろうと、そう確信めいたものを抱いていた。
それは、長谷部が柊の元に通い始めて半月が経った頃だ。初めてこの地に降り立った頃から変わらず、太陽はあまねく全てを焼き尽くさんとしている。正午よりは少し日が傾いてはいるものの、アスファルトの車道からは熱気が吹き上がって、空気がゆらゆらと揺れている。
「にゃあ」
長谷部が柊の元へと向かって歩いていると、耳慣れた軽快な挨拶が聞こえてきた。まだらの猫――ロキは、初日とまったく同じように、道の途中で長谷部に合流し、彼を店まで先導する。毎日甲斐甲斐しく迎えにくるものだから、使い魔疑惑はあながち間違いでもないかもしれない、と長谷部は一人苦笑したことがある。今日もいつも通り塀を伝って長谷部の前をつかず離れず歩いていくものだと思っていた。しかし、ロキは歩いていた塀から歩道へと降り立ち、そのまま長谷部の方へと向かってきた。
「いて、いてて。今日は一体どうしたんだよ」
長谷部の手前まで駆けてきたロキは、長谷部のズボンにしがみつくようにして爪を立て始めた。布を貫通して皮膚にまで届く爪はもちろん痛いが、それよりも、いつも聞き分けの良いこの猫が珍しく粗相をしている点が気になった。見たところ長谷部自信に敵意を抱いている、という様子ではないが、何かに怯えているような必死さが感じられる。長谷部の足を容赦なく引っかきながら、にゃあにゃあと絶えず訴え続けている。
「まさか――」
嫌な予感がして、長谷部は走り出した。ロキがその後を着いてくる気配を背中に感じるが、構っていられる余裕はない。流れる汗と激しく収縮する器官も忘れて、一目散に柊の店へと駆けていく。
程なくして、目的の建物へとたどり着いた。一見して建物に変わった様子はなく、いつもの通りに開店中の札が立てられている。しかし、店の周囲を覆う木々はほんの僅かな風にもざわざわと音を立てて、長谷部の胸騒ぎをいっそう大きいものにした。
蒸し暑い気温と打って変わって冷えきった指先でガラス戸を開けても、やはり店内に異常はない。相変わらず空気は不思議と涼しく、静寂に包まれている。柊の姿は入口からは見えない、しかし――
「……っは、」
小さな呼吸音が、澄んだ空気を僅かに震わす。それは音の主の判別が難しいほど微かなものではあったが、長谷部は疑う暇もなく店の奥へと急いだ。果たしてそこには、地に膝を追って蹲る、この店の主の姿があった。
「ハリウッド!」
長谷部は慌てて駆け寄り、柊の背中に手を添えながら顔を覗き込む。俯いた顔には長い前髪が完全に影を作っていてうまく窺い知ることはできないが、着物の襟から見える白いうなじには、珍しく薄い汗の膜が浮いている。添えた手のひらからは小刻みに震える感触と、調子を整えようとする大きな呼吸の動きを感じる。羽織に隠れて見えなかったが、どうやら胸の辺りを押さえているようだ。
「意識ははっきりしてるか? 待ってろ、今救急車を……」
早口に声をかけて慌てて携帯電話を取り出した長谷部の腕を、柊の震える手が引き止めた。
「おい、そんな状態で我慢なんて――」
「……頼む、このまま…………」
切れ切れに紡ぐ声と、前髪の隙間から射抜くような瞳は、今までに見たことがない必死さを湛えていた。
+++
コンロの上で、小さめのやかんがしゅんしゅんと音を立てている。茶葉を入れた急須にお湯を移して、開けた和室へと運んだ。部屋の真ん中には布団が敷いてあり、すっかり落ち着いた柊が静かに眠っている。
――結局、あれから医者を呼ぶようなことはなかった。長谷部は初めこそ迷ったが、同じように病弱な姉の看護でこういった事態は慣れていたため、とりあえず様子を見ることに決めた。
勝手知ったる調子で居住スペースに布団を敷いて寝かせる頃には、柊の顔色は元に戻っていた。苦しみに耐え続けた身体は疲れきっていたようで、まるで息を引き取るように(本当に心配した)穏やかな眠りについた。眠りに落ちた柊の呼吸は極端に気配がなく、意識して耳をそばだてなければ呼吸音を聞くことはできない。この部屋の静寂を取り込んでいるみたいだ、と長谷部は思った。
店を訪れた時刻から三時間が過ぎている。この時間に姿を消すほど真夏の太陽は殊勝ではないが、いつの間にか降り始めた雨とそれを司るぶ厚い雲に遮られて、窓からは薄明かりが差し込む程度になっていた。それに伴って珍しく気温も冷え込み、寒気の残る背筋を誤魔化すようにして、長谷部は熱い緑茶を啜った。あぐらをかいた長谷部の目の前の柊は目を覚まさない。寒気が気温だけのせいではないことなどわかりきっている。
更にそこから二時間が経過し、用意した茶はすっかり冷め切ってしまった。長谷部はといえば、何をするでもなく、柊に視線を向けながら遠くを見て、じっと考え事に耽っていた。彼は医者を呼ぼうとした自分を止めた柊の、その目を知っていると思った。遠い昔、彼の姉が発作を起こしたときにも同じような目をしていた。自分に近づく終わりの運命について、抗いたくないと訴えるその目。諦めてしまっているわけでも、面倒に思っているわけでもなく、長谷部の姉や柊は、自らその運命に従うことを“選択”していた。その心根がいかなるものか長谷部には測り知ることができなかったが、長谷部はその選択を是とし受け入れた。そうすることが当然に思えたからだ。結局、彼の姉は生死の淵を彷徨った末に、ギリギリのところで生き残った。意識を取り戻した姉もまた受け入れたような目をしていたので、なぜだか強く印象に残ったことを覚えている。とある作家の元へ嫁いで以来連絡をとっていないが、そういえば元気にしているだろうか、と長谷部は暢気なことを考えた。
「――」
意識が散漫になり始めた頃、柊が身動ぎ一つしないまま瞼だけを持ち上げた。
「ハリウッド! 起きたのか」
「……ああ、世話をかけた」
目を覚ました柊が目線だけをこちらに向けて温度のない礼を述べると、いつも通りの様子でなんでもないように身を起こすので、一瞬介助する手が遅れてしまった。
「おい、あまり急に動くな。体に障るぞ」
「問題ない……助けは不要だ」
柊の肩に添えた手に軽く触れて促され、長谷部は心配そうにしながらも元の位置に座り直した。彼の言う通り、顔には血の気が戻っている(と言っても普段から生気が薄いが)し、動きにも無理をしている部分は見当たらない。しばらく横になって回復したのだろうか。
柊の具合が良くなったことを確認すると、長谷部はおもむろに口を開いた。
「お前、死ぬのか」
それはおおよそ寝込んでいた人間にかける言葉ではなかったし、口にした本人すら動揺しているほどだが、柊は色のない表情のまま、眉一つ動かさなかった。そしてそれこそが、この空間において最も雄弁な返事だった。
柊は僅かに口を開いて、再び閉じた。それは何かを言いかけて思い直す仕草であり、柊が見せる表情の中では初めてのものだ。永遠とも一瞬とも感じられる時間が過ぎ、噤まれた口は再び開かれる。
「再会とは、なんだと思う……?」
まったく話の流れを汲み取れない、それは唐突すぎる質問ではあったが、長谷部は静かに柊の言葉を聞いた。それを語ることが彼にとっては今何より大切なのだと、長谷部にはわかっているからだ。
「以前に会った人物にもう一度会うこと……とかいう話をしたいわけじゃないんだろ?」
「……人間を、個人たらしめるものは何か……。変わった変わらないなどと、他人に対し評価を下す状況は多くあるが……その要因の多くは、自身の内側にある。人間が、決まりきった“個人”から完全に脱却できることは……そう多くない。また、そもそも――どんな人間の“自己”も、大抵は幻のようなもので……他人にその全貌を掴むことは……まずできないだろう……。そんな中で変化を感じる、あるいは不変を信じるということは……己の内に投影した、虚構を相手にしているだけだ……」
「ああ、そういったことなら何度か経験があるかもしれない。変わったとか変わってないとか、知ったようなこと言う奴ばっかりだな」
「そう――それは同時に……相手にそうあってほしいという、自らの願いでもある……。相手に変わっていないと願いをかけ、自らの内に存在する虚構との再会を祈る……。再会は、そうした願いの蓄積だ。……だからこそ、己が内を変えなければ、いつでも望むように再会できる……」
取り留めのないことを、大気に溶かすように呟くのは、この短期間ですぐに分析できる柊の癖だ。彼は目の前の長谷部に語りかけているようでありながら、聞かせる気がない語り口調は独り言にも思えた。長谷部はそれに適当な相槌を打って、ゆるやかに流れる時間に身を任せるのが定石だ。しかし、今の長谷部にそんな余裕はない。まっすぐ柊の方を見て、一言一句聞き漏らしたくない緊張で、握った両の手に力を込める。それに――
「だから、」
柊はそこで言葉を切って、ゆっくりと口を閉じてしまった。今の彼は、明らかに様子がおかしかった。相変わらず遠くを見ている視線は、しかしどこか熱に浮かされているようでもあって、語っている言葉は、手渡されるほど身近に感じられた。まるで、
(自分の思いを言葉にしたがっているようだ……)
長谷部が視線を落とすと、掛け布団の上に投げ出された柊の左手の近くには、握ったようなシワが微かに見て取れる。もう開く様子のない唇は注視すればすぐにわかるほど力んでいて、伏せられた睫毛は消え入りそうな印象と裏腹に、確かな決意を湛えているようだ。この先を口にするまい、という柊の態度が、やがて訪れる運命を忘れさせるほど、長谷部には好ましかった。
後から考えればおかしな話ではあるが、この時長谷部はたしかに、「変わったな」と思った。それはもしかすれば、柊に対しての「変わってほしい」という願いのためかもしれない。しかし、今この場所での長谷部にはどうでもよかったし、未来の彼にとっても、意味のないことかもしれなかった。
勢いを削がれた雨がぱらぱらと屋根を打ち付けて、やがて満月がその姿を現すだろう。時刻は午後九時になろうとしている。
◇◆◇
柊が倒れていたその日からも、長谷部の訪問は変わらず続いている。二人の会話になんら変化はなかったが、柊はたびたび発作を起こすことがあった。その度に長谷部が介抱しており、一度も医者を呼んだことはない。柊を蝕む病についても、治るものか治らないものかすら、長谷部は何も知らない。長谷部は聞かなかったし、柊も言わなかった。
照りつける灼熱の1ヶ月の間を、長谷部は柊と過ごした。店内の丸椅子でぽつぽつと喋ることが多かったが、時には柊の居住スペースに居座ることもあった。常に長谷部は冷たい茶を、柊は熱い茶を、すっかり手に馴染んだ湯呑みに用意した。いつかに柊がかなり古い湯呑みだと語っていたが、詳細についてはよく知らない。柊は掴みどころのない哲学のような話と、長谷部の身の上話を好んでいるようだった。身の上話と言っても大した内容ではなく、仕事で扱った記事や、撮影に訪れた土地や、それに伴った彼の考えなどが主だった。話を聞くたびに柊は遠くを見て、少しだけ目を細めるのだ。初めこそ表情の意味を測りかねた長谷部だが、何度も観察する内にそれが懐かしんでいる眼差しだとわかった。まるで長谷部を通して誰かを思い出しているようで、無性に落ち着かない気持ちになる。長谷部も柊の昔の話を聞きたいと振ってみたこともあるが、途方もないほど遠い昔の、それこそ長谷部が調査中の五百年前の話などをされて、怪訝な顔をする結果となった。直後に柊が肩を揺らして笑うものだから、長谷部はからかわれたのだと、この話題について聞き出すのは諦めた。ただ、その笑みが何かをごまかしているように長谷部には感じられたが、気のせいだと結論づけて、記憶の隅に追いやった。
その土地に滞在する一ヶ月はあっという間だった。撮影や取材と記事の執筆、柊の店への訪問を繰り返し、長谷部は人生で最も充足を感じている。しかし、そんな生活にも終わりが近づいていた。明日、滞在していた宿を出て、都会へと帰ることになる。
「楽しかったよ、ここにいる間」
古物店の中で向かい合って腰掛けて、いつもの通り手には湯呑みが握られている。明日に出発する話をしていた、その中の発言だった。柊は長谷部の話にも顔色一つ変えず、静かに相槌を打つばかりだった。緩く頷いた動きで、長い前髪がさらりと揺れた。
「悪かったな、なんか……毎日通っちまって」
「構わない……元々、人が来る場所でもないからな……」
そう口にする柊は湯呑みの茶をゆっくり傾けて、静かに瞼を閉じた。空気に耳を寄せるようなこの仕草も、柊の癖だった。微塵も乱れがない柊の様子を、長谷部は焦れた表情で見つめる。
「……なあ、その……寂しいとか、ないのか」
抑えが効かずに、ついにはそんな子供じみた言葉を口にしてしまっていた。言ってしまった本人はしまった、とばつが悪そうに口ごもっているが、柊はそう言われることをわかっていたかのように、静かに笑みをこぼした。
「なんだ……別れを惜しんでほしかったのか」
「いや、まあ……そうだな」
からかっているようで、その実微笑ましく見守るような声音で言われてしまえば、長谷部はますます居心地が悪くなってくる。まるで駄々をこねる子供のようだと自分でも思うが、それを受け入れられないのはますます大人げないので、彼の言葉を素直に肯定した。少し熱の上がってしまった顔を隠すように頬に手を当てた。柊が更にくすくすと声を漏らすので、しばらく熱が下がることはなさそうだ。
「お前は――またここに来るだろう。……別れを惜しむ必要もない」
笑う声音は変わらないが、先ほどのようにからかう様子は一切感じられない。それが当然であり、定められたことだとでも言うように、柊が口ずさんだ。思わず長谷部が勢いよく顔を上げると、柊は眩しそうに細めた瞼と薄く浮かべた笑みで、長谷部を見ていた。長谷部はガラス戸を背にしているため実際に眩しかったのかもしれないが、長谷部にはどうでもいいことだった。
長谷部にとっては、この地に滞在する一ヶ月がタイムリミットに思えていた。この地を離れ、柊と別れることを柊自身が受け入れた途端に、もう二度と会えなくなってしまうような、そんな焦燥に駆られていた。だからこそ子供じみたことも口にしてしまったし、不安の滲む表情を隠すこともできていなかった。しかし、柊はこの先も長谷部と会うことを望み、当たり前のように語った。それは長谷部にとっての“許し”であり、雲間に射す太陽のように、長谷部の不安を晴らしたのだった。長谷部自身はそんな自分の思いを正確に把握できてはいなかったが、ただなんとなく、こみ上げる安堵に身を任せた。わけもわからないまま静かに涙をこぼす長谷部を、柊は更に目を細めて見つめている。それは彼にしては珍しく、後悔のような、罪悪感のような視線だった。
「悪い、突然。もう大丈夫だ」
「――いや。……京輔、」
目元に残る水分を片手で拭う長谷部に、柊はゆっくりと首を振った。それから立ち上がって、すっかり空になった長谷部の湯呑みを預かる。しかし、おかわりを入れるために奥へ歩き出すことはなく、座る長谷部の前に立ち、じっと彼を見下ろしている。見上げる長谷部には、口を引き結ぶその顔が泣き出しそうに見えた。思わず柊の空いている左手の手首の辺りを握ると、柊の纏う空気がふっと解けた気がした。
それからは、いつも通りだった。空になった湯呑みを再度満たして戻ってきた柊と、とりとめもない話をして、暗くなってから店を出た。明日の早朝には電車に乗る予定だから、今晩は早々に荷造りをして寝てしまわなければならない。見送るように途中まで隣を歩いてくれたロキに、「またな」と声をかければ、「みゃあ」と返ってきた。宿に戻ればさっさと支度を済ませて、11時前には床に就く。我ながら白状だと思ったが、長谷部は寝るまで柊のことを思い出さなかった。それは暇がなかったからかもしれないし、柊の言葉から得られた安堵からかもしれない。
都会へ帰ってからしばらく、長谷部の日常は目まぐるしく過ぎていった。記事を提出した会社に打ち合わせをしに行って、自分の記事は受理されたのだが、同じ特集で書くはずだった別のライターが不祥事で蒸発したとかなんとかで、長谷部にもその皺寄せが押し付けられた。そもそもこの会社の所属でもないのにあり得るのか? などと苦々しい独り言を漏らしたりもしたが、世話になっているため無碍にもできず、穴埋めするように自らの記事を大幅に改稿する羽目になった。なんとか仕上げたはいいが今度は身内の不幸があったとかで十何年ぶりに実家に帰ったりして(ついでに姉が元夫と離婚し再婚までしていたことを初めて知った)、心身ともに休めるようになる頃には、照りつける太陽も鳴りを潜めた、秋の入口になっていた。
諸々の用事が一段落した長谷部は、駅のホームで電車を待っている。平日の朝では相変わらず駅は混雑しているが、片田舎に運ばれていくこの路線を使う人間は少ないらしく、ホームにはぱらぱらと数人が立っている程度だった。右手の切符を懐かしむようにまじまじと見つめ、丁寧に手帳へ挟んだ。彼の休日は柊の元へと訪れることに決めていた。
電車に揺られること二時間、すっかり昔に感じてしまうその土地に降り立った。今度は宿に寄ることはなく、まっすぐ柊の店へと歩き出した。当然だが一ヶ月程度で歩道も塀も風変わりするなんてことはなく、そこいらに生えている鬱蒼とした木々が少し元気がなくなったように感じる程度だ。目的地までの半ばほどまで歩けば、軽快に木の葉を踏む音と共に、涼しげな声が転げてきた。
「にゃあ」
「久しぶり」
ロキは返事でもするように再度ひと鳴きすると、長谷部の少し前を先導する。時間が経っても同じように迎えに来てくれる彼を、長谷部は嬉しく感じていた。もしかしたら柊が自分を歓迎してくれているのかもしれない、と思ったからだ。長谷部が今日ここに来ることは柊には知らせていない(そもそも連絡先を知らない)ため、そんなはずはないとわかっているのだが。
同じように向かった先には、変わらない古物店が静かに鎮座している。長谷部は密かに安堵していた。どこか、あの日々が幻だったかもしれないという不安が付き纏っていたからだ。店を囲む木々の中には気の早いものもいて、青々としていた葉をすっかりと赤く染めている。店先の開店中の看板を見つけて、長谷部は足取りも軽くガラス戸の前に立った。引き戸に手をかけたがすぐには開かず、口元だけで小さく深呼吸してから、極力平常心を装って開いた。
「……ハリウッド?」
店の中は記憶のとおり、素っ気なく並べられた陶器類と、不思議にひんやりとした空気が漂っている。柊はいつも店の奥の、居住スペースのある方から出てくるため、覗いてみたが姿が見えない。突然の来訪のため、単に気づいていないか、あるいはどこかに出かけているだけだろうか。長谷部はそう考えたかったが、いつ訪れても、柊は自ら歩いて長谷部を出迎えた。顔を見せなかったのは――
「まさか……!」
さっと長谷部の血の気が引いて、前のめりに歩き出す。あっという間に長谷部の頭の中を嫌な予感が埋め尽くした。もしかしたら歩けない状態なのかもしれない、もしかしたらまた発作が起きて、もしかしたら――
「……おかえり」
奥に向かう長谷部の背後に、ぼそぼそとした色のない声がかけられる。振り向いた先には、棚の整理でもしていたのか、売り物と思しき皿や器をいくつか抱えている、陰気な男が立っていた。まるで「仕方がないな」とでも言いたげに苦笑する表情の意味を、長谷部は知ることはできなかったが、そんなことを考える間もなく長谷部はその場にしゃがみこんだ。
「びっくりさせるなよ……」
「それは……すまないな」
柊は手近な棚に持っていた商品を置いて、大きくため息をつく長谷部の目の前に、視線を合わせるように膝を折る。しゃがんだままの長谷部は少し高い場所にある柊の顔を情けない表情で覗き込むが、柊は変わらず微かな笑みを浮かべていた。長谷部は安心したように頬を緩める。
「ただいま」
少しだけ埃かぶった丸椅子をはらって、馴染んだ調子で腰掛けた。そこから先はいつも通りで、また柊と話ができることを、心から嬉しく思ったのだった。
◇◆◇
更に一ヶ月が経った今でも変わらず、長谷部は暇になると必ず柊の元を訪れている。最低でも週に一度は顔を見に、時には仕事を持ち込むこともあって、文字通り”入り浸る”という表現が正しいほどだったが、柊はそれを咎めるどころか喜んでいるように思った。
歩道に木の葉を散らす木々はすっかりと衣装を変え、ほんのりとくすんだ赤色が視界の端を占めている。しばらく取り掛かっていた仕事を終えた長谷部は、いつものように柊の店への道中を歩いていた。初めてこの道を歩いたときとは打って変わって、乾いた冷たい空気に入れ替わろうとしている。もう間もなく冬が訪れるだろう。過ごしやすい季節だというのに、秋の逃げ足はめっぽう早い。
風の冷たさに比例して、柊の発作が多くなってきたように思う。身体に障る時期だから当然かもしれないが、それでも長谷部は気を揉まずにいられなかった。そんな身体だというのに、柊の格好がいつまでも夏と同じような装いであるせいかもしれない。冬にも変わっていなかったらさすがに怒ろう、と長谷部は決意している。
店に到着すると、柊が自ら歩いて出迎えてくれたため、長谷部は内心ほっとした。そんな長谷部の内心を知ってか知らずか、慣れた様子で茶を入れるため奥に引っ込んでいく。
いつもは丸椅子に腰掛けてじっと柊を待つ長谷部だったが、今日は壁に作りつけられた棚の一点を見つめ、おもむろに商品を手に取った。それは盃だった。手の中にすっぽりと収まるほど小さいそれは、なめらかな白い陶器の肌に、紺色の線で桔梗の描かれた代物だ。古物の価値に精通していないため長谷部に値段のほどは計りかねたが、気になった点は高級品か否かなどではなかった。
「なあ、なんでこれは売られたんだ?」
二人分の茶を入れて戻ってきた柊に、振り返りざま問いかける。柊は一瞬不思議そうな顔をしたが、長谷部の手に握られた盃を見て合点が行ったようだった。
盃には金継ぎの跡が残っていた。しかも小さいものが複数箇所あり、継ぎ目は極力目立たないよう繊細に施されていた。腕の良い職人に任せていたのだろう。そんな風貌の盃が、汚れひとつ見当たらない。丁寧に手入れされていた様子だった。素人の長谷部でも、長い間大切にされていたものだと見当がつく。それが今、古物店に売られているという様子が、妙にアンバランスだった。
「それは……遺族が持ち込んだものだ……」
柊は静かに語る。代々受け継がれた盃を祖父から譲り受けた持ち主が病死した際、遺品の整理をしていた遺族が見つけ、売りに来た。遺族曰く「彼のように大切にできる気がしない。誰か他の人に大切にされた方が、この盃も本望だろう」とのことで、これを手放したそうだ。長谷部から言えばそんなものは建前で、少しでも金になればと思ったんだろうことは想像に難くない。しかし、柊にとってはそんな本音や建前など瑣末なことに過ぎず、ただ静かに、盃に満たされた歴史を飲み下しているようだった。
「受け継ぐ、というのは……そういうものだ」
「え?」
唐突な話の切り替えに、長谷部は戸惑ったが、それはどうやら長谷部の考えていたことを見透かした上での言葉のようだ。末恐ろしいな、と思いつつ、長谷部はその先を促した。柊が緩慢な動作で頷く。
「次の主に思いを受け継ぐ……よくある話だが、それは所詮……譲り渡す側の願望であり、幻にすぎない……。譲渡する側と、される側……その両者の精神には必ず……明確な違いがあるものだ。人はそれを無意識にでもわかっているからこそ、変えないでほしいと思いながらも、よりよく変えてほしいとも……思っている」
「……」
「……受け継がれる物に込められているのは、意思などではない……。それは、願いだ。未来に繋いでほしいという、何かを変えてほしいという、望みだ。だから、たとえ責任の重さから逃れるためだとしても、はした金を受け取るためだとしても、どちらでも変わらない……。その器には、多くの時間とともに、すべての持ち主の願いが満たされている」
ガラス戸の外の光をぼんやりと見つめている柊は、まるで自分を語るように饒舌だった。口元を覆い隠したような、ぼそぼそとした声量は変わらなかったが、長谷部はそう語る柊の目に宿った光を見逃さなかった。それは長谷部が初めて、柊が柊自身のことを話してくれたような、そんな実感を得た瞬間だった。
「これ、俺が買ってもいいか」
気がつけばそう口にしていた。思わず、といった具合ではあるが、それは長谷部自身の心のままに放った言葉だったから、驚くこともなく柊を見た。柊は外から長谷部へと向き直り、ほんの少しだけ、目を見開いた。それから口元をゆるめて、ゆっくりと目を閉じた。柊からこれほどに強い感情を向けられたのは、この先にもついぞないかもしれない。それは喜びだった。
「……ありがとう……」
それが店主としての言葉でないことくらい、長谷部にはわかっている。桐の箱にしまい込まれたそれを、長谷部は厳かに受け取った。柊自身から手渡されたそれを、大切に抱えているとなぜだか泣きそうになったが、ぐっとこらえた。
◇◆◇
――あの暑い日を覚えている。蜃気楼の向こうに置いたはずの心は、いつの間にか幻そのものを美しいと思ってしまった。その心だけは本物だと、彼ならば言ってくれるかもしれない。
柊にも長谷部にも、その時が近づいていることは気づいていた。そしてそれから目を逸らすことは、おそらく彼ら自身が、最も許し難いだろう。
冷えた空気が肌を突き刺していく。灰色に濁った空からは軽い雪が次々に落ちてきて、木々の色を失くした道を白く染め上げようとしていた。柊の元へ歩く長谷部は傘も差さず、降り注ぐ雪に身を任せ、歩道よりも白く曇る息をひとつ吐いた。この辺りの雪は風が吹かない限り積もりやすいらしく、わざわざ誂えた雪道用のブーツで、転ばないよう慎重に歩を進める。
十二月の終わり頃、世間がにわかに騒がしくなるこの日も、長谷部は柊の元へ訪れようとしていた。なんの誘いもなかったと言われれば嘘になるが、それよりも柊に会いたいと思った。それは前向きな感情であるとともに、まるで追い立てられるような、焦りのせいでもあった。長谷部はそれをうっすらと感じているし、柊自身には更にはっきりとわかることだろう。
道の半ばにたどり着いても、ロキの迎えはなかった。寒さに弱い猫のことだから、動けなくても当然かもしれないが、しかし長谷部にとっては、それは宣告のように感じられた。
(今日で最後かもしれない……)
突然でもなんでもない、決まりきった出来事だった。
古物店にたどり着けば、店の前の札は閉店中と書かれていた。長谷部の記憶にある限りそれは初めてのことで、なんだか見ていられなくて裏返して立てかけ直した。ポケットから手を取り出して引き戸の取っ手に触れる。手袋をしていないためかじかんでいるはずだったが、その手は震えてはいなかった。戸を開いた先、果たしてそこには、長谷部の予想した通り、柊は迎えに来なかった。声をかけずとも、長谷部にはその意味がわかっていた。頭と肩の雪を簡単に払って、ため息をひとつつく。無意識に詰めていた呼吸を促すためであったが、わずかに安堵の色を含んでいることを、長谷部自身も知っている。
誘われるように、店の奥へと歩みを進めた。いつもの丸椅子は、奥の会計机の横に並べて置かれていた。その様子だけは、長谷部の心臓をひどく締め上げた。更に奥にひっそりとある扉を開けると、蝶番がすすり泣くように声をあげる。聞き慣れた音だった。ドアの先は靴を脱ぐスペースの他は一段高くなっていて、木の板の床と襖で構成された、小さな和式の居住区だ。入ってすぐ目に入る左手の襖の先が柊の寝所である。何度も訪れたこの場所は、こんな日であっても特別な気配など一切なくて、いつも通り素っ気ないままだった。だからこそ長谷部はいつも通りに、その襖を開いた。
寝所である和室の中心には一組の布団がしかれていて、その上に柊が静かに横たわっていた。長谷部にとって見慣れた光景だったが、今日のそれがいつも通りでないことは、ここに来る前からわかっている。足音を立てようと目を覚ます様子のない柊の側へ腰を下ろすと、大きく息を吸った。
「おい、起きろよ」
語りかける声は長谷部が思う以上に和室全体を震わせた。それはまさしく長谷部の思いの強さそのものであり、最後にもう一度だけ声を聞きたい、縋るような願いだった。
一瞬の後か、それとも一時間か、曖昧な時間が過ぎて、勿体ぶるように柊がゆっくりと両目を開く。目を覚ました姿勢のまま、柊は視線を動かさない。しかしその意識がはっきりしていることは、長谷部にはよくわかっていた。
「もういいのか」
あまりにも端的な長谷部の言葉はまるで会話になどなっていなかったが、二人の間には他の誰にもわかり得ない、通じ合う何かが出来上がっているようだった。柊はその言葉に耳を傾けるようにして、再び目を閉じた。かけられた布団の胸元が一際大きく上下する。
「元々……ほんの少しの間だけ与えられた、奇跡と呼ぶ他無い時間だった……。むしろ、長すぎたくらいだ……」
柊の声には悔いや未練がなかったし、その表情に終わりへの恐れは見られなかった。ただただ運命を受け入れるその姿が、今の長谷部にはなぜだかひどく腹立たしく、また悲しく思えた。
「そうじゃないだろ」
「……なに……?」
長谷部は夢中で、半ば絞り出すように言葉を紡ぐ。彼自身は、自分の頭に浮かぶこの感情が、言葉が一体何に由来しているのかわかっていなかったが、それでも声を発することをやめられなかった。
「お前はこうして、またこの世界に存在することができたんだろ。それはお前の意思がそうさせたんじゃないのか。いつもいつも運命だ世界だって、こうして会えたんだからもうそんなもの捨てちまえよ」
「京輔……」
長谷部にはもう何がなんだかわかっていない。言葉が理性を追い越すごとに、その声は悲痛さを増していく。喉を引き絞るように発せられる叫びは、すでに子供の駄々と同じで、理屈もへったくれもない、支離滅裂なわがままだ。そんなことは長谷部にもわかっていた。わかっていたけれど、最後に言わなければならないと強く思った。ずっと言えなかった言葉を。
「奇跡とか偶然とかそんなんじゃないんだよ。お前が強く望んだから叶ったんだ。これが夢でも幻でも、俺がお前と再開できたのは間違いないんだよ。俺の中のお前と、今のお前と、何も変わってなかった。だからいいんだよこれで!だから……お前の、望みを、願いは、」
勢いに任せた言葉たちは、次第に砕けて意味を成さなくなっていった。それは長谷部の思いが途切れたわけではなく、その涙によるものだった。彼は恥も外聞もなく、顔をくしゃくしゃと歪めて泣いていた。それでも止まない洪水のような声を聞いて、柊は長谷部を静かに見つめた。その瞳はかすかな驚きと一緒に、慰めるような色を含んでいる。こんな状態にあって尚、いっそ緊張感がないほど、柊は長谷部をあやすように手を伸ばして、止めどなく涙の溢れる頬を撫でる。そうすれば長谷部の眉尻がいっそう情けなく下がって、柊は困ったように笑った。
長谷部は必死だった。自分の思いを伝えようとしても、内側から溢れてくる意味のわからない衝動に押し流されて、自身の願望を上手く掬いだせない。何かがあったはずだった。柊と出逢ったときから抱いていた、たった一つの望みが。すべてが夢のようで蜃気楼のようで、一瞬の後には消えてしまいそうな世界でも、絶対に失くすことのできない願いが。それは長谷部の与り知らぬ長い長い間大切に仕舞っていて、埃被って見えなくなってしまうほどのものだった。
長谷部の苦悩を柊は知ってか知らずか、長谷部に触れる手はますます優しく、彼を宥める。長谷部がそれを思い出せるまで待ってくれると言わんばかりの、甘やかすような視線だ。涙は相変わらず流れ続けたままだが、長谷部の顔には笑みが浮かんでいた。泣いているのか笑っているのかわからない、不格好な表情ではあったが。
「俺は、お前が、」
「うん」
「お前に、」
「うん」
柊の声はどこまでも優しかった。目はすべてを包み込むように細められた。頬に添えられた手は今までで一番暖かくて、血の通った人間である事実が長谷部の心を揺さぶった。それから、すとんと落ちるように納得した。とても簡単な、子供みたいな願いだった。
「お前に言ってほしかった」
「うん」
「俺と会えてよかったって」
それだけだった。それが長谷部京輔という魂が残した願いの、たったひとつだった。それだけを言って、長谷部は口を閉じた。彼の瞳は風のない水面のように静かだ。しかし今度は柊が、その目を零さんばかりに見開いている。照明を受けてきらきらと反射する瞳が綺麗で、長谷部は思わず前のめりになって、柊の目尻に触れた。一粒だけ、静かに雫が落ちた。
(やっとだ)
長谷部の心はすべて満ち足りた。柊のその顔が見られたのを、長谷部はきっと忘れないだろう。たとえどんなに長い先の未来であっても。ふと、あの盃が思い浮かんだ。あれを気に入ったのはきっと、柊に似ていたからだ。
(俺はお前を、少しでも満たせただろうか)
柊は長谷部を見つめて、長谷部も同じように見つめ返した。彼らはとっくに覚悟を決めていた。柊は己に添えられた長谷部の手を自分の手で掬い取り、これで十分だと言うように、柔らかく握った。
「京輔」
「なんだ」
握った長谷部の手に額を押し当て、柊は呼びかけた。長谷部はこれ以上ないほど甘やかに返事をする。先ほどと立場が逆転していて、二人は同時に失笑した。続く言葉が、柊の最後の言葉になるのだろうか。長谷部は少しだけ、握る手に力を込めた。
「また会おう」
欲望の濁流に押し流されてしまいそうだった。それは強すぎるあまり呪いとも言えるような願いであり、意思であり、彼自身が初めて見せた、彼だけの欲だった。有り余る歓喜で長谷部の心は引き千切れそうに叫んだ。柊がまるで遊びに行く約束をする子供のような顔で笑うので、長谷部も心のままに笑った。それで最後だった。
いつの間にか長谷部の意識は途切れて、暗闇へと放り出された。
◇◆◇
長谷部京輔はカメラマンである。懇意にしてもらっている雑誌の連載企画の関係で、とある街に訪れている。そこは山々に囲まれた片田舎で――と言っても中途半端に利便性のある――都心から電車で二時間ほど揺られた場所にある。彼は一年前にもこの土地で撮影したことがあるが、今回は別の企画を用意されている。なんでも田舎の実態に関する特集をするとかなんとかで、自分の元にこの辺鄙な田舎の依頼が舞い込んできた。舞い込んできたというよりは押し付けられたに近く、中途半端なこの場所は、特徴がなさすぎて誰も書きたがらなかったみたいだ。
(人を便利屋みたいに扱いやがって……)
心中で独りごちるが、そんな悪態で腹立たしさが収まるわけでもない。首からぶら下げたカメラといくつかの荷物を持って、自分が一週間ほど滞在する宿に向かった。
車は少ないが活気はそこそこにあり、しかしやかましいということはなく、なんというか――のどかだ。相変わらず中途半端な場所だ、と長谷部は思った。撮影のために、午前は街を歩き回ってみる。ついでに以前の滞在での土地勘を取り戻すためだ。
さて、この地形はいわゆる盆地である。季節は七月、時刻は正午を回っていて、真上の太陽は燦々と、いや爛々と、景気よく世界を照らしまくっていた。
「あつい……」
そう漏らした声は誰にも聞こえるはずはなく、ゆらめく熱気とともにアスファルトへ吸い込まれていった。当たり前のように湿気は高く、汗を吸い込んだシャツが肌に貼り付いてこの上なく不快だ。そんな中、長谷部は民家も店もない街外れの歩道をとぼとぼ歩いている。木々だけがやたらと元気で、ぬるいを通り越して温かくなったスポーツドリンクは、ちゃぽちゃぽと音だけは涼しげに響いた。首にかけたカメラのストラップが鬱陶しい。しかし手に持つことも叶わず、腹の辺りで揺れるままにしている。
「にゃあ」
塀の上の木陰から声が転がってくる。落ち葉を踏みしめる音とともに現れたのは、薄汚れたサビ猫だった。猫は更にひと鳴きすると、長谷部に背を向けて彼の少し前を歩き始める。まるで着いて来いと言わんばかりの様子に、長谷部は素直に従った。
程なくして、長谷部はそこへ辿り着く。鬱蒼とした木々の隙間に、まるで隠れるようにして木造の家が立っている。ガラス張りの戸は民家でないことを示しているが、看板も何も立っていないため、店であるともわからない。その前に、建物をぐるりとツタが囲っていて、相当に古く、人の手を離れてから時間が経っていることを示していた。長谷部がおそるおそるガラス戸から中を覗き見ると、中には棚らしきものが作り付けられてあるようだが、特に何も並んでいない。そのまま引き戸を開け放てば、積もった埃が勢いよく舞い散った。咳き込みつつ改めて中を窺っても、どう考えても人が出入りしてる場所ではなかった。放置されて5年以上は経過していそうだ。天井の隅には蜘蛛の巣が張り巡らされて、作り付けられた棚板も劣化してぼろぼろに崩れかけている。奥にひっそりと置かれた二つの丸椅子は、使われていないことを示すように、材料の木がささくれ立って、やはり埃が積もっている。
長谷部は一番マシに思える会計机に荷物を置いて、ぶら下げたカメラで写真を撮った。何かを刻むように、あるいは、写真を通して自分の記憶をこの場所に刻みつけるように。気が済むまで撮り終えると、今度は荷物の中から花束を取り出して、丸椅子の上に乗せた。同じく取り出した桔梗柄の盃にペットボトルの水を満たすと、花束の上にすべて垂らした。儀式めいた一連の行動だったが、長谷部自身には特に理由などない。ただ単に、大切にしたいという思いを形にするための、継ぎ接ぎな行為だった。
埃っぽい中、満足げに大きくため息などついたので、思い切り咳き込む羽目になったが、なんとか持ってきた荷物を持って外へ出ると、店先には先ほどの猫がちょこんと座り込んでいた。
「久しぶり」
長谷部は猫をひとなですると、抱えてきたものの中で一番大きい荷物――ペット用のキャリーケースの中にその猫を招き入れて、再び抱えて歩き出した。慎重に運ばれるケースの中で涼を取る猫と裏腹に、暑さに身を任せながら、長谷部は住んでいる場所のペット相談に思いを馳せている。
(駄目だったら、最近仲良くなった姪やその知り合いにも当たってもらおう)
夏は暑さとともに狂おしいほどの幻を連れてくる。幻は果たして現実だったのか定かではないが、それを美しいと感じた自分は本物だ。少なくとも、長谷部はそう願ってやまない。
「ああ、会いたいなあ」