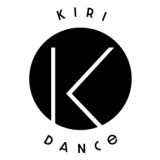繰り返される規則的な揺れで目が覚めた。薄ぼんやりともやのかかった視界は黄色いような赤いような、奇妙な箱のように見えるので、夜が近いのだなと、覚醒しきってない頭で考えた。何度か瞬きをすれば向かいの座席と、つり革と、興味のない広告がはっきりと見えて、ここが電車の中であることがわかる。自分たちの貸切電車のようで、他に乗客は見当たらない。肩にかかる心地よい重みは不安定だ。まだ眠っている親友が快適にまどろんでいられるよう、ゆっくりと体勢を整える。整えて、すぐ近くにある顔を覗き込んだ。いつもくるくると目まぐるしい表情は鳴りを潜めて、今はただただ静かに目を閉じている。嬉しいとか、苦しいとかそういう感情もなくて、穏やかに眠っている顔に安堵した。窓から差し込む光を受けた髪は、人工的に色を抜かれていて、少々不自然な輝きを放っていたが、それも彼女らしいもので、好ましいとすら思っている。
光の元を辿るように首を反対側へと向ければ、太陽が水平線に溶けかかっていた。窓を開けていないのでわからないが、外は潮の匂いでいっぱいだろう。窓からは何かの木の葉と、砂浜と、切り立った崖と、一面の海しか見えない。それからふと、どうしてこんなところにいるのか思い出そうとした。そもそもどこから来たんだっけ。ずっと長い間電車に乗っていた気がする。朝からずっと、乗り慣れない電車に乗って、乗り継いで、人が減っていくのを眺めながら、誰もいないような路線を終点まで。いくら記憶を掘り返しても理由がわからないので、自分の肩で健やかに眠る親友の頼みだろうと結論づけた。いつもそうだった。彼女は突拍子もないようなことを言うが、それに意味がなかったことなんてなくて、真っ直ぐに彼女を信じることができた。彼女の願いならばなんでも聞いてやるつもりだった。大切な優しい親友の願いだから。
何も思い出せないまま少しの時が過ぎて、電車の中に終点を知らせる声が響いた。オレが未だ眠り続ける親友に短く声をかけると、彼女は開ききらない目をこすりながら、小さくあくびを零した。まだ少し足元の覚束無い彼女を気遣いながら電車を降りると、そこは小さい無人駅で、当然のように自分たち以外は誰もいない。改札にしてはお粗末な出口からは一面の海と砂浜が見て取れて、ぼんやりと覚醒しきらない親友も少しずつ気分を上げていった。どうやらここは彼女の望んだ場所で間違いないようだ。
車がまったく通らない割に広く舗装されている道路を我が物顔で横断して、簡単に作りつけられた階段を降りる。設備や砂浜は汚れてこそいないが、手入れはなんだか中途半端で、そこかしこに雑草や少しのゴミや、流されてきた壊れた傘なんかも落ちている。今は時期じゃないから後回しにされているんだろう。
親友は完全にいつもの明るさを取り戻して、もたつきながら靴を放り出すと、波と戯れながらはしゃいでいた。ひらひらと広がるスカートを履いているので、時折裾なんかを気にしながら、存分に水の冷たさを堪能している。砂浜でその様子を眺めているオレに手を振って、それから、少し深いところへ歩みだした。スカートの裾がつくギリギリまでの深さで、もう一度彼女はこちらを振り返った。
「凪!」
いつも通りの太陽と同じ色の声で名前を呼ばれて、自然とそちらへ足を踏み出すと、彼女は大きくかぶりを振った。不自然に輝く薄い色の髪がぱさぱさと舞っていたので、仕草の意味はどうでもよくなった。一歩を踏み出した姿勢のまま、動けない。
立ち止まるオレを満足そうに眺めて、彼女はまた一段階深いところへ遠ざかる。スカートの裾は水面で広がってしまって、お気に入りだと言っていたのに勿体無いな、と思った。彼女が後ろを向いたので、オレはまた歩みをはじめる。今度はこちらを振り返らない。靴も脱がないまま波打ち際へたどり着く。波はすぐにオレの足をさらって、まとわりついて、重くした。更に歩を進めようとしたが、うまく歩けない。波は粘ついたように重かった。無理やり踏み出せば着地点の定まらない足はあっという間にバランスを崩して、その場に片膝をついてしまう。立ち上がりかけた姿勢で彼女を見やれば、ますます遠くへと離れてしまっていた。とっくに沖の方にいるはずなのに、沈んでいる様子はなく、オレのように足を取られた様子もない。ただひたすらに水平線へと歩いている。もう少ししたら、あの太陽と一緒に溶けるのだろうか。
重く粘つく波は歩を進めるごとに密度を増しているように感じられるが、それを不自然には思わなかった。足を取られて転ぶことを無様だとも思わなかった。彼女の元へ行くのに邪魔だな、とだけ思った。彼女との距離は離れていくばかりなのに、オレは名前を呼ばなかった。呼んでもどうしようもないことを知っていた。
一歩進んで、ガクンと沈む。また一歩進んで、沈む。もう鎖骨の辺りまで水に浸っていても、歩みを止められなかった。呼び止める声はいらない。呼吸のための鼻も必要ない。溺れるのは怖くない。彼女を見失わないための目だけが残っていればよかった。よかったのに、砂を蹴る足は無情にも何もない水中に放り出されて、波はオレの姿を飲み込んでしまう。
最後にもう一度だけ名前を呼ぶ声が聞こえて、それきりだった。
◆
よく響く誰かの笑い声で目が覚めた。一瞬で明瞭になる視界には見慣れた部屋が広がっていて、とっくに覚醒しきった頭が、ここは自宅のベッドの上で、笑い声は外を歩いている女学生か誰かの声だろうと結論づける。いつも通り、鳴る前に目覚めてしまうため特に意味のない携帯のアラームを切ってから、適当な服に着替える。朝食の匂いがするのは、更に早起きをした弟によるものだろうか。
ずっと同じような夢を見ていた気がする。はっきりとは覚えていないが、旅をするような夢を。そして旅の先には終わりがあって、今朝、終わってしまったんだろう。
窓から差し込む光は時刻を主張するように灼けている。もう二度と同じ色を見ることはできない。