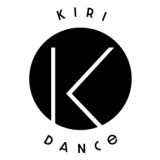K2Web再録本の小説部分です。
全部氷室と一人。
タイトルクリックで本文が出てきます。
漫画・イラスト部分はこっち→お歳暮
練るね
「で、これが話題の知育菓子ってやつ」
パキョ、という軽い音を立てて、プラスチック製のトレイの隅を切り取る。外袋からバラバラと飛び出した粉末の袋たちは、古びた学習机の上に無造作に置かれたままだ。水をどうしよう、と思っていたら、一人が自分の水筒を差し出してきた。使え、ということらしい。
「今度はどこに行ったんだ?」
「んー、なんだっけ。浅草?」
俺の両親は何かと行動力があって、一年に何回かはこの辺鄙な村を飛び出して、華々しい都会へ連れて行ってくれる。村の生活も悪くはないが、やはり新たな刺激は日々に潤いを与える。やがては村の外に住むんだろうな、とぼんやり考えたこともあった。
目の前の友人を上目にちらりと見る。机の上の袋をまじまじと見つめているこいつは、あまり外の世界を知らない。この村唯一の病院の跡取り息子で、それはそれは厳しく育てられてるそうだ。休みの日は修行とか勉強とかしてると言っていた。げーっと思う。
サラサラ。一番の粉を入れる。放課後の教室は斜めに傾いた夕焼けを受け入れている。休みの日は遊べないから、こうしてときどき放課後に残ってちょっと遊ぶ。俺は、旅行に行くたびに一人が驚くものはないかな、と探すようになった。勉強も運動も敵わない一人に対して、優越感を得るためのただ一つの方法だ。
「俊介」
「なに?」
「実はこれ、やったことある」
「は!?」
がばっと顔を上げたら、なんとも言えない表情で一人に見られた。最悪だ。地味にウキウキしてる俺の方が後輩ってわけだ。あと、物珍しいものをこうして持ってくる理由もバレているらしい。
「先に言えよ」
「お前の親切を無碍にはできない」
「親切じゃないっつーの……」
ぼやきながら慎重に水を量る。あーあ、かっこわりい。荒い動作でトレイに水を加えて混ぜる俺を、困ったような一人が見つめる。哀れんでんのに、親切だなんて言われるとは、こいつも大概お人好しだな。
「お前は流行りのお菓子なんてろくに食ったことないんだろーなと思っただけ」
「そうだな。村の外に出ても、親父にねだったことはなかったな」
「ねだればいいだろ」
「遊びに行ってるわけじゃない」
「かてーやつ」
十分に混ざった一番の粉と水の上に二番の粉をぶちまける。さっさと混ぜてしまおうと思った手が止まる。赤い日差しの中でトレイを見つめる一人の目がきらりと光っている気がする。
「……やる?」
「いや、俊介は初めてなんだろ」
「別にやりたいわけでもねえし」
もともとお前のために買ったようなもんだし、と心の中で付け足して、小さなプラスチックスプーンを一人の手に押し付けた。納得行かないながらも承知した一人が、ゆっくりとトレイの中をかき混ぜる。粉と水が混ざったそれは、もこもこと泡立ちながら色を変えた。
「……」
無表情の瞳が楽しいと訴えている。トレイの中の光景にほんのりとわくわくしている。俺はそれを、頬杖つきながら見るわけだ。あの優秀な一人坊ちゃんに俺が勝ってると思えるから、だから浮ついた気分になっているんだろう。小学五年生だから、あまり詳しいことはわからないけど。
わけのわからんふわふわがまとわりついたスプーンを、一人の手から奪って口に含む。変な甘さで全然美味しくないという顔をしたら、クスリと笑った一人が、「トッピング忘れてるぞ」と言った。だからなんだよ。先輩風吹かせやがって!
将来の夢
畑と畑に挟まった小道を歩けば、両側から甲高い虫の大合唱が鳴り響く。手にしたプリントも負けじとぱたぱた揺れるが、ほんのささやかな秋風ではどうしようもない。
『将来の夢は?』
プリントの真ん中で拙い文字が主張している。学校からの帰り道はいつも俺と一人のふたりきりだ。隣を歩く一人と俺の足音がばらばらに空気を揺らす。
「将来の夢、かー……」
俺たちももう小学六年生で、目の前で揺れるプリントは卒業文集のための用紙だ。クラスの誰かが手書きで一生懸命したためた記入用紙をコピーして、今日クラス全員に配られた。一人ずつこれに書き込んで冊子にして卒業前に配る、そういう趣旨のものだ。背負ったランドセルとの別れを感じて子供心にしみじみする。
「とりあえず高校まで行って、大学も行きたいんだよな。それから村に帰ってくるか都会に出るか……」
出来上がる卒業文集に心を弾ませて、クラスの面々の例に漏れず俺も休み時間の間でほとんどを記入し終わったが、この『将来の夢』欄だけが埋まっていない。あまり具体的に自分の未来を想像したことがなかったのだ。作文に書かなきゃいけないときは、なんとなくその場しのぎで書いていた。これといってやりたいことがない上に、両親の金銭的余裕もある家だから、選択肢も絞れない。運動も勉強もそつなくできる方だと自負しているし、あと多分俺は将来ハンサムになる。子供の拙い知識では職業の想像にも限界があり、もやもやして何もわからなくなってしまった。公務員?銀行員?ITってやつの会社とか、モデルなんてのもありか?
「一人は? やっぱり、医者になりたいのか?」
隣で黙々と歩を進めていた一人に声をかけた。一人を挟んで反対側に傾いた大きな太陽があるから、逆光になった一人の表情がよく見えない。村唯一の診療所の息子で、後継ぎとして待望されている一人は、いつも医者としての教えを叩き込まれているらしい。当然診療所を継ぐものだと、俺を含めた誰もが信じて疑わない。
「なりたいとかなりたくないとかじゃなくて、なるんだ」
太陽の沈む音すら聞こえた気がする。一人の声を合図にしたように、虫の声も、風に揺れる草のざわめきも、砂利を踏むふたりの足音も、体中を走る血液の音も消えてなくなった。世界が支配されているのだと思った。
「俺はそうなんだよ、俊介」
足を止めた俺の三歩先で一人が振り返った。いつもどこか必死にすら見える重たさを抱えた瞳に、今はなにもない。静かで、凪いで、これ以上話すことはないと訴えかける。村に住む大人たちとよく似た目をしていた。村の掟について、診療所について、外れにある墓について、詳しいことを聞こうとするときにする瞳だ。子供の俺には何も聞かせることなどない、と口を噤む。
息が詰まっていることに気づいて空気を吸い込んだら、笑えるほど不器用に肺が膨らんだ。幼い頃からなんでも話せると思っていた親友が、俺に壁を作ってガラス玉みたいな瞳を向ける。いっそ逃げ出してしまいたかったが、最後の意地でその場に立ち尽くした。見かねた一人が「俺はもう、帰るから」と歩き去った。踵を返す一瞬、少しだけ見せた苦しげな表情が頭に焼き付いて離れない。
勢いの良い風が吹いて、持っていたプリントを空中に運んでいった。やっと音が戻った世界はすっかり暗くなっていて、振り切るように家路を走る。今はまだ、一人を追いかけて何がなんでも聞き出すことなんてできそうになかったが、やがては知らなければならないと思った。知らなければ、前にも後ろにも進めないと思った。
そして一年が経って、俺の未来はただ一つに決定する。
伴侶
古びて鳴き声をあげるドアを押し開ければ、一面に広がる青空と心地よい風が吹き抜ける。少し高く作りつけられたフェンスのすぐそばに見知った背中。最近またぐんぐんと背が伸びたみたいで、伴って大きく広くなっていく背中だが、ひとりで佇んでいるときのそれは不思議と頼りない。昼休みなのにがらんと開けた屋上で、上下真っ黒のシルエットがぽつりと浮いている。
「ほい、C組の佐和子ちゃんから」
周囲いわく近寄りがたい雰囲気を発しているらしい友人の隣に遠慮なく並び、手に持っていた封筒を渡す。可愛らしい水玉の封筒には丁寧にハートのシールで封がされていて、中身を見ずともどういった内容かわかる。
「ああ、ありがとう」
手渡した友人――一人は、全然嬉しそうじゃないどころか、困った顔をしながら手紙を受け取った。
「また断るのか?」
こういうことは珍しくない。俺ほどじゃないが、一人はモテる。顔のつくりは整っているし、背も高い。その上成績優秀で運動もできて、同級生に見えない落ち着きで大人びている。しかしどうにも話しかけづらいということで、友人の俺の元へ、ラブレターを渡してほしいという依頼が舞い込んでくるのだ。別に直接話してみれば気のいいヤツなのにと思うが、愛想がないから仕方のないことかもしれない。
そして今までもらったたくさんのラブレターのうちの、一枚たりとも色よい返事をしたことがない。保留の返事すらなく、必ずすっぱりと断っているらしい。女子泣かせなヤツだな、と思う。
手紙に一応目を通している一人が、気まずそうに「まあ、うん」と返事をする。佐和子ちゃん落ち込むだろうなあ。しかし一人が決めたことに、俺がどうこう言う理由もない。
「付き合ってみようとか思わないのか?」
軽い雑談のつもりで聞いてみた。こいつが軽い気持ちで交際をするヤツではないことはわかっているから無意味だと思うが、聞いてみるだけならタダだろう。一人はうーんと唸って、
「この先ずっと一緒にいるなら、志を同じくできる人じゃないと、幸せになれないと思うから。俺もその人も」
と答えた。付き合う人と当然のように人生を共にする前提なのが堅物のこいつらしい。一時の青春とかそういう概念はないのか。
たしかに、一人の生い立ちや宿命とも言えるものは、実に特殊だ。俺も秘密を打ち明けられるまでは、そんな世界があるなんて夢にも思わなかった。医療に身を捧げるだけでなく、俺たちの住む村にずっと縛り付けられる人生というのは、たしかに生半可な覚悟では共にすることができないだろう。その因縁を考えるといつまでも胸がざらざらする。
「でもさ、志云々の前に、お前は自分の秘密を話してないだろ? 言ってみたら、意外と覚悟を決めてくれる人もいるかもよ」
自分で言いながら、それはどうだろうか、とも思う。所詮俺たちはまだ子供だ。将来どのように生きるかを現実感を持って決めるのは難しい。今覚悟したところで、この先気が変わらないとも限らない。
「……怖いのかもな」
フェンス越しの景色を見るともなしに見て、一人がぽつりと呟く。たしかに、神代家がやっていることは非合法で、有り体に言えば犯罪だ。無闇に秘密を漏らせば危険が伴う。それだけでなく、秘密を知った人間によっては、恐ろしいと思い一人を強く拒絶する者も現れるだろう。いくら一人が強いと言ってもそれなりのダメージがあるはずだ。ちょっと無神経だったかと焦って、慌てて言葉を紡ぐ。
「じゃ、じゃあもう秘密を知ってる人ならいいんじゃないか」
そう、すでに秘密を知って受け入れている間柄ならば、怖がることもない。少し目を丸くした一人が、言いづらそうに「……お前しかいない」と呟いたので、屋上には気まずい沈黙が落ちた。俺しかいないのか。
ふ、と告げられた言葉を噛み砕く。一人の秘密を知っている同年代は俺しかいないらしい。なるほど、いつも同級生たちから一歩離れたような距離感で接しているのも頷ける。なんとなく負い目があるというか、心から親しめる気がしてないんだろう。そしてそれは、どれほど寂しいことだろうか、とも思う。俺たちが悠々と過ごしている間、こいつはひとりで秘密を抱えて、ひとりで勉強して修行して、そのままひとりで生きていくつもりなのか。
「俺なら一緒に頑張れるぜ」
たまらない気持ちになって、口からぽろっと溢れた言葉を、しかし意外なほど冷静な頭で続ける。
「俺は一人の秘密を知ってるし、それで友達やめようとか思わない。それに志とやらも同じくできる。お前と同じように医者として人を治すし、なんならすごい研究して医学に貢献したりするんだ。お前よりうんと活躍してやる」
子供の馬鹿げた自信だが、不思議と叶わないという気持ちは起こらなかった。一人と約束するときは、必ず叶えてやるという決意のみがある。呆気に取られている一人になんとなく溜飲を下げて、頭に浮かんだまま言葉を続けていく。
「俺は外の世界に出ていくから……もしかしたら距離は遠いかもしれないけど、ずっと一緒にいようぜ」
気張らずさらりと言えた気がするが、それでも照れくさくなってうなじの辺りをぽりぽりかきながら俯いて眼下に広がる街を眺める。一人が黙ったままなのがまた居心地悪い。なんか言えと催促のつもりで横目で視線をよこしたら、珍しいくらい柔らかく笑っていた。思わぬ表情に驚いて、恥ずかしさとか気まずさが屋上から落っこちてなくなってしまった。
「俊介」
「な、なんだよ」
「不束者だがよろしくな」
「はあ?」
意味がわからん、をそのまま顔に出していても、一人はフフフと笑うだけで何も答えず、予鈴と一緒に屋上を出ていってしまった。
なんとなく屋上を出る気になれなくて、五限はこのままサボってしまおうとその場に寝転んだ。遮るもののない青空が痛いくらい目に突き刺さってくる。目を閉じても、わけもわからず浮足立つ心に眠りを妨げられた。
***
「今思えば、あれプロポーズみたいなもんだったな……」
「いいから帰ってくださいよ氷室さん」
約束
線路が別れを連れてくる。強風に木々が揺れ葉を振り落とす、春だ。
肌寒い朝一番のホームには誰もいない。しんとした構内には放送の音も電車の音も響かない。始発電車まで時間があるからだ。
隣に座る友人の顔を窺い見る。長距離の移動にしては少ない荷物を膝に抱えて、珍しくその顔にはなんの表情も浮かんでいない。いつも騒がしい相手の沈黙は、こうも落ち着かないものだったろうか。
「荷物それだけなのか」
「おう、残りは全部あっちに送ったからな」
友人――俊介は、俺の方に顔を向けて答えた。その表情には見覚えがあって少し安心した。小さなボストンバッグひとつで表情を見せないまま旅立つ俊介が、違う人間に思えたのかもしれない。いっそ山ほどの荷物を抱えていれば印象も違うだろうか。
俊介は村を出る。中学校を卒業し、東京の高校へ進学することを機に、両親ごと引っ越すのだそうだ。もちろん、高校の合格が決まった時点でそれは聞かされていたから、今更驚くことはない。いつも厳しい父さんが「いってきなさい」と、朝の修行もしていない俺を送り出したことだけが、まるで重大なことのように胸の奥につっかえている。ただ進学をするだけだ。東京はどうしても行けないほどの距離じゃない。電話も手紙もある。
「一人〜」
いつの間にかこちらににじり寄ってきた俊介に、眉間をぐりぐりと押されている。「ヒビ」とだけ言って手が離れていった。考え込んだせいで表情に力が入っていたようだ。
膝に置いてあるボストンバッグに上半身を預けて、俊介が白んできた空を見上げる。
「寂しくなるよなあ」
「えっ」
「おいなんだよ、お前は寂しくならないのか!?」
俊介が苦い顔をこちらに向けてくるが、完全に虚を突かれた形の俺は、間抜けな顔のまま放心してしまう。思いの外、“寂しい”という言葉がつっかえる胸の奥をするりと通過した。
「いや、寂しいよ。うん……寂しいな」
腹まで落ちてきたそれを噛み締めるように繰り返せば、俊介が「あ〜びっくりした」と苦笑する。
生まれた村で医者になるという使命を、そうやって死んでいく生を、不自由に感じたことがないと言えば嘘になる。しかし、人を救う使命に誇りも持っているし、今では受け入れている。だからこの友人についていくことはできない。できないことは言ってもしょうがないから、言うべきことは何もないと思っていた。
(こうやって話してもいいのか)
腹まで落ちた感情はやがて消化されて血肉にもなるだろう。別れの朝にヒバリがエウレカと鳴いている。
***
太陽がすっかり顔を覗かせて、時計の針を急かしてくる。相変わらず人はいないが、構内の放送は流れ始めた。もうすぐ始発が来るらしい。
結局、俊介と他愛のない話をして時間を潰した。なんでもない思い出の間に「寂しい」と挟みながら、俊介と一緒にそれを咀嚼した。俊介はいつもどおり騒がしい。
「俊介はやっぱり医者になるのか?」
「あたり前だろ!東京に何しに行くと思ってるんだよ」
「でも、お前はなんにだってなれるだろ」
「お前に約束したんだから医者の道しかないぞ」
このやり取りもいつもどおりだ。子供の頃から絶対に一度決めたことを曲げない性格だったが、まさかここまでとはと驚かされることもしばしばある。
両親をはじめとして、医に携わる者の生き方を心から尊敬しているし、俊介が医者になるというのも応援している。ただ、俊介がたびたび口にする“約束”は、つまり“俺のため”だ。俊介の人生が俺の手に握られているようで、どうしても気になってしまう。
「モデルは?」
「おま、それ小学校の頃の話だろ。まあ俺ならできると思うけど、ないな」
「IT企業とか」
「興味ねー。なしなし」
「銀行員」
「一人」
咎めるように名前を呼ばれ、咄嗟に口を引き結ぶ。俊介の顔は怒っているようでいて、何よりも緊張が前面に押し出されていた。
「俺は後悔しないし、後悔させない。お前よりすごい医者になって、“この道しかなかった”って言わせてやる」
ボストンバッグを右手にぶら下げて俊介が立ち上がる。座っている俺と向き合うように振り向けば、昇る太陽も俊介の背に隠れてしまう。逆光でも、こちらを真っ直ぐ見据えながら笑う顔ははっきりと見えた。
「一人、お前の一族はたしかにすごいよ。でも俺はもっと世界に出てやる。この世界の医学を根底から進歩させる」
ホーム中に列車の到着を告げるベルが鳴り響く。俊介は少し深く息を吸い込んでいた。このベルの音に負けない声で伝えようとしているのは、水晶体の奥に宿る炎を見ただけですぐにわかった。
「お前たち一族の魂を俺が伝える!」
電車が走る音にもかき消されることはない、灼熱の意志が鼓膜に伝わる。ひたすらに真っ直ぐであり、空恐ろしい執念すら感じる宣言だった。なんということはない、この俺が野暮だったのだ。氷室俊介という人間が抱いた夢は、たとえきっかけとなった自分といえども折ることはできない。ただただ決意を胸に走り続けるだろう。俺のためであり、どこまでも俊介自身のためでもある。
俺もベンチから立ち上がり俊介と視線を合わせる。つい目を細めてしまうのは、電車の窓越しに見える朝日のせいだけじゃない。どこへ行っても俊介は俊介のままだ。俺が俺のままでなくなっても、きっと。
空気が抜けるような音が耳をつんざく。線路が連れてきた別れが口を開けて待っている。
俺は何も言わず右手を差し出した。慌ててボストンバッグを左手に持ち直して、俊介も右手を差し出してくる。無言の握手は言葉以外の感情を交わすものでもあり、適切な挨拶が見つからないのをごまかすものでもあった。俊介はずっと俺と共にある。共にある者を送り出すための言葉を知らない。
***
駅のホームは静かだ。次の電車は一時間後らしい。ポケットの中の入場券を手で弄びながら、線路の先をじっと見る。
しばらく会えないという確信めいた予感がある。それでも胸に灯る約束は、寂しさを燃焼して推進力に変えてくれる。駅員に乗車券を渡して改札をくぐり抜ければ、少し背筋の伸びたいつもの朝だ。
強風で木々も山も電線もざわざわと揺れている。遠ざかる電車だけが、まっすぐな音を鳴らしている。
矜持
カチカチカチカチ……。無意味な音が自分だけの室内にこだまする。無意味も無意味、受話器を取っていない電話のボタンを押したとてなんの意義もない。衝動を逃すために電話機に八つ当たりをしている。
「それやめてくださいよ、氷室さん」
「スミスくん。でも受話器は取ってないぜ」
「研究室の備品で遊ぶなってことですよ。これ、こないだの結果です」
いつの間にか研究室内に入ってきていたらしい後輩の同僚――スミスくんが、俺のちらかったデスクに紙の束を器用に乗せる。ちらりと一瞥してパソコンのモニターに視線を戻した。スミスくんの声色から、とっくに結果はわかっている。
「これ何回目でしたっけ」
「百……あー、ぱっと出てこないな」
実験データをすべて格納しているフォルダを開く。ずらっと並ぶファイル数にこめかみが痛くなって、数えるのをやめた。椅子の背もたれに上半身を預けて天井を仰げば、まぬけに開いた口から盛大なため息が漏れる。こんな姿はとてもじゃないが親友に見せられない。
時刻は二十二時、研究室はここからが本番だ。真っ暗な窓の外と蛍光灯に照らされた室内のコントラストが目に痛い。日本は今昼頃だろうか。疲れたときにはどうしても思考が故郷へ帰りたがる。机に投げ出された右手がまた自然と電話機へ伸びて、カコカコと軽快にタップし始めた。身体に染み付くほど何度も押した番号を無意味になぞる。
「かけたらいいじゃないですか」
「…………」
ふたつ隣のデスクに座っているスミスくんが、呆れた顔でこちらを睨めつけた。お決まりのやり取りではある。彼には、俺と故郷の親友のことを(言えるところだけ)直接話したことがあったから、尚更そう思うんだろう。
「そう簡単じゃないんだよなあ」
「はあ」
「これはなんか、意地っつうか矜持っつうかな」
スミスくんに話したことで少し気が紛れたのか、あの診療所の電話番号を押す手を離すことができた。とっくに昔の番号だから変わっているかもしれないのは承知だ。承知の上で、そこに縋っている。
「アイツと約束したんだよ」
「それは聞きました」
「なんの成果も上げずに帰るなんてかっこ悪いだろ」
「そんなもんですかね」
かっこ悪さという理由は本心でもあり、方便でもある。電話をかけない理由は、主に親友への負担になってしまうことが大きい。彼は今、あの村で大きな使命を背負いながら医術を磨いているはずだ。とっくに一人前の医者として人々のために働いてもいるだろう。俺の心配事まで聞かせる必要は、ない。
アメリカで臨床と研究を往復する生活は、充実していて熱中できる分、ストレスも多い。単純にやることが多すぎるし、研究の進みを実感できることも稀だ。先ほど預かった紙の束をめくれば、やはり実験は思い通りにはいかない。思い通りにいかなかったデータにも重要なヒントがあるために失敗とまでは言えないが、暗闇で手探りするような不安がいつも付き纏う。
更に言うなら、人種差別が根強い環境で、アジア人がなんの苦労もなしにただ成果を評価されるわけもない。研究、論文執筆、制度利用、その他色々な場面で白人たちより明らかな冷遇を受けてきたが、持ち前の対人能力でなんとか今の環境をもぎ取った。それでも本来無用な苦労をしている疲労感は抜けない。そういう面もあって、同じような境遇のアフリカ系アメリカ人であるスミスくんとはよく話すようになった。俺が一方的に話してるような感じもあるが、彼もそんなに嫌がってない、と思う。多分。
親友に電話して声を聞くと、それらの愚痴が全部こぼれてしまいそうなのだ。きっとアイツは一切嫌な顔をせずに聞いてくれる。でもアイツは愚痴なんか言わない。そういう奴だから、どうしても負担が偏ってしまう。
「約束が俺を医者たらしめてる。もしアイツから帰ってこいなんて言われたら、ぐらっと揺らぎかねないんだよな」
「それはどうなんですかね」
冗談めかして嘯いた言葉に、しかしスミスくんは若干の真剣さを交えて応えてきた。なんだその子供を諭すような目は。歳上に向かって。
「氷室さん、もうしっかり医者だと思いますけど」
「医者だよ」
「そうじゃなくて。約束とか関係なしに、医者としての使命みたいなのを持ってるんじゃないかってことです」
思わぬ言葉に、ゆっくり大きく瞬きをすれば、目から鱗がぽろぽろ落ちる。先日この眼球を傷つけたガラス片も落ちている気がする。
「患者さんとか、もっと新しい医療が必要な人とか、そういう人たちのことを考えてる氷室さんも本物の医者だと思います」
「はは、あんまり褒めるなよ」
「表情筋ぎこちないですよ」
スミスくんの言葉を咀嚼するのに時間がかかっている。自分の人生は親友との約束に捧げたものと思っていたが、たしかに思い当たる節はあるのだ。本格的に医療に携わりはじめて、人を治すことに生き甲斐というものを覚えている自分を。こんな重労働の毎日でもやっていきたいと思える燃料が、約束だけではないことを。しかし――
「不誠実じゃなかろうか」
「は?」
「約束したのに、アイツ以外のために生きるってのは……」
心に浮かんだ言葉をそのまま漏らせば、スミスくんは「もう勝手にしろ」とでも言いたげな苦々しげな顔をした。俺ほどじゃないが器用な表情筋だ。食傷だとでも言わんばかりの空気がこちらまで伝わってくる。
「親友さんも氷室さんがそういう医者になることを望んでるんじゃないですかね」
「君にアイツの何がわかるんだ」
「めんどくせえ~、家帰ってください」
スミスくんはヘッドホンをしてデスクに向き直ってしまった。もうお前の話を聞く気はないの姿勢だ。いつもならここから二十分ほどお構いなしに絡みにいくのだが、今日は考えることが多くなったので俺も大人しくモニターをぼんやり見つめる。
約束は、俺が医者であることを運命づけたただ一つの理由だ。でもその先は――医者で在り続けるためには、約束だけでは足りないのか?
モニターに並ぶ研究データの向こうに、親友の顔と並んで、これを必要とする患者の顔が浮かぶ。足りないのではなくて、大切なものが増えているだけなのだと、頭に浮かんではいてもまだ腑に落ちていない。たしかに一度帰宅して寝た方がいいのかもしれない。
時刻は二十二時半。日本は今昼頃だろう。あるはずもない親友からの着信が耳奥で響くようだ。あるはずもないのなら自分から会いに行けばいいのか、と考えたところで、シャットダウンしたモニターは真っ暗になった。反射して映る自分の顔は、思いの外清々しい。