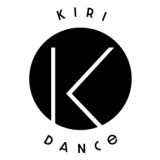龍の目(桐真)
決して折れることのない不滅の眼差しが、真正面から射抜いてくる。
1、2、3。まるでダンスでも踊っているかのような軽快さに、しかし勢いと重さを乗せて、目の前の男を翻弄する。上から、下から、横から、予測の難しい奔放な攻撃を、男は的確に捌きながらも、僅かな隙を見逃さない。男めがけて高く振り抜いた右足に沿うように拳を押し出す。寸でのところで上体を反らすことでその拳を避け、ついでに喉から「ヒヒッ」と笑い声を漏らす。崩れた重心をそのままに地面に手をついて、回転しながら男の脛の辺りへ蹴りを繰り出しても、やはり避けられた。勢いを利用して体勢を整える。間合いを取って、お互いに大きく息を吐く。
「ゴッツいのぉ、桐生チャン」
「…………」
肩で息をする相手は、今この時も自分から目を離さない。
(また、その目ェかいな……)
自分と互角――いやそれ以上の桐生との喧嘩は、一瞬たりとも気を緩めることができない。まして闘いの最中に相手から視線を外すなど以ての外。桐生もそれは同じなのだろう。喧嘩中は、必然的に桐生と何度も視線を絡ませる。バチリと音がしそうなほどの熱量とともに。
以前に桐生の目は光を失っていないと言った。それは2年ほど経った今でも嘘になっていないし、そんな桐生の目を好ましく思っている。それはもう、嫌になるほど。
桐生の目は真っ直ぐだ。ただ真っ直ぐなだけでなく、様々な澱を沈めて尚、不屈だ。これまでに幾度となく大切なものを得、そしてその多くを失い、何度も折れかけただろう。しかし絶対に光を失わなかった。継ぎ接ぎの意志は相まみえるたび強固になる。どんなことがあっても、この男は得ようとする。守ろうとする。くらくらするほどの馬鹿正直な生き方だ。
息を整えた桐生が、ぴんと張り詰めた眼差しをこちらに向ける。冷たいほどに熱い、闘志と、興奮と、そして少しの。
(わかりやすいやっちゃ。ホンマ)
世界で5本の指に入るほどわかりすいこの男の、自分に向ける眼差しの意味に気づけないほど鈍くはない。めらめらと奥に燻るような思いには覚えがある。何故なら自分もまた、この男に同じ感情を抱いている。
桐生がアスファルトを蹴って、こちらの懐に潜り込んできた。咄嗟に顎を打とうと持ち上げた膝はいなすように右手で横へと払われ、何も身につけていない胴へ桐生の拳がめり込んだ。まともに食らった。せり上がってくる胃液だか血だかをぐっと飲み込み、よろけてたたらを踏んでしまうついでに後ろへ下がった。桐生がそろそろ終わりかと言いたげな視線を寄越す。まだ終われるわけがないだろう。挑発的な笑みを浮かべれば、桐生は見慣れた構えを取った。話が早い。
拳の隙間から桐生がじっと見据えてくる。視線の中に含んだ思いは、喧嘩が始まるときからずっと変わらない。否、もっと前からだ。明け透けで隠そうともしていないのかもしれない。
ごめんだった。多少の種類の違いはあれど、自分を強く求める桐生の目は、他の――桐生が守り、そして時に守りきれなかった多くの大切なものを見るときと同じだ。その眼差しを注がれては、まるで自分が桐生の大切な、輝いていて、美しくて、慈しむべきものにでもなったような気持ちになる。馬鹿らしい。その目を向けるべきは自分ではない。
自分があの目に弱いことは十分にわかっている。だからこそ、のらりくらりと先延ばしにしてきたわけだが、そろそろ潮時だろう。瞳の奥の情動は濃度を増している。この喧嘩が終わったときか、次に会ったときには、桐生はその胸中を開示する。元々回りくどいことが苦手な男だ。自分を本気で得ようとするこの男から、逃げられる自信は正直、ない。
「兄さん、」
(あ、)
まずい。目算を誤った。桐生は喧嘩を終える前に、今この時に、決着を付けようとしている。なんて我慢のできない男だ。考えるより前に、自分の足が地を蹴って、持ち前のバネで高く飛び上がる。虚を突かれた桐生の元へ着地するように高度を下げると、桐生はあっさりと仰向けに倒れ込んだ。背に昇る応龍が軋む音がする。倒れた桐生の腹に馬乗りのまま、その目をじっと見つめる。
「……!」
上体を傾げて瞼を降ろさぬまま桐生と唇を重ねれば、大きく見開いた瞳が動揺で揺れている。気分がいい光景だった。
そう、この男はどこまでも鈍い奴で、こちらの思いになどまったく気づいていないことこそが、自分のアドバンテージだった。不意を突くのは容易だ。動揺から醒めやらない桐生を眺めて、自分の笑みが深くなるのを感じる。
龍の目にとことん弱いのだから、きっとこの男の求める願いを、これからも受け入れてしまうのだろう。しかし負けっぱなしは自分の性に合わない。どんな隙でも見逃さず、貪欲に勝利を望んでこそ真島吾朗というものだ。
「桐生チャン、よぉ聞けや」
組み敷いた男の間の抜けた顔が目に映る。まずは1つ、勝ち星をもぎ取ろう。
未読(桐真)
眠らない街神室町。日が落ちた程度ではこの街の明るさを奪うことなどできない。太陽光よりもギラギラと目に痛いネオンは、しかし今日の自分の気分ではない。自然と人のいない方、より静かな暗がりへと足が向かう。
左手に代わり映えしない工事現場のバリケードを眺め、その先にある西公園が見える。げっ。思わず顔を顰めてしまった。
「おお、桐生チャンやないか」
西公園でいつも火が焚かれているドラム缶の、その傍らには常日頃自分を追い回す兄貴分の姿がある。手袋越しの指に吸いさしの煙草を挟んで、幾分かリラックスした姿勢だ。しかしこの男のスイッチは何がきっかけで入るかわからない。今日は暴れる気分でもないのだ。喧嘩を売られる前に、さっと踵を返す。
「ちょ、ちょお待てや。今日は喧嘩する気分やないねん。なんもせえへんから、休憩に付き合うてくれんか?」
所構わずハイテンションで喧嘩を吹っかけてくる真島の珍しい態度に驚いて、返した踵を元に戻す。こちらをじっと見るその眼差しには覇気がなく、眉尻も戸惑い気味に下がっている。約束を違える男ではないから、この休憩で何か手荒なことが起こる心配はなさそうだ。こちらの反応が過剰とでも言いたげな声色には納得がいかないが、好奇心が勝って「いいぜ」とだけ短く返事した。
真島と同じようにドラム缶の側に立って煙草を口にくわえると、隣から火のついたライターを握った手が伸びてくる。面食らってぱちりとひとつ瞬いたが、厚意に甘えて顔を近づけた。吸いなれた匂いが鼻をかすめる。
「アンタに接待してもらえるとはな」
「こうでもせんと、桐生チャン帰ってまうかと思ってなあ」
わざとらしくしなを作った声で真島が答える。ご機嫌取りの類を嫌うこの男のことだから本心ではないとすぐにわかる。自分をもてなしたい故の行動だろうか。時折見せる真っ直ぐな好意に、思わず顔が綻ぶ。
ライターをしまった真島が紫煙を吐き出しながらぽつりと話しはじめる。「今日な、」と呟くような声がする。
「なんか寂しいねん。事務所だーれもおらんし」
ぼんやりと焚き火を見つめる瞳に感情は読み取れない。本当に寂しがっているかどうかは伺い知ることができないが、真島がこうして寂しさを口にするのは度々ある。冗談めかしてるようにも、本気で寂しさを埋めたいようにも聞こえる。
「せやから、桐生チャンがおってくれて助かったわ」
こちらを見てにっと笑う。喧嘩中にいつも見ているはずなのに、初めて見たような笑顔だ。実際に落ち着いた状況下で見たのは初めてだったのかもしれない。歯並びが綺麗だとか、目を細めると涙袋が目立つとか、細かいことに気づいた。ひと呼吸置いて発言の意図を噛み砕き、隣にいるのは自分以外の誰でもいいと言われているようで、項の辺りがちり、と焼ける気分になる。口にくわえている煙草をひと吸いして、燃えて短くなるそれに自分を重ねた。「自分は特別」と言われたかったのだろうか。どうかしている。いつも通りじゃないこの場なら、調子も狂うというものだ。真島がすっかり短くなった煙草をドラム缶の中に捨てる。自分を煙草に重ねたばかりの身には、なんだかその気のない動作が無性に物悲しい。
ドラム缶を名残惜しむようにじっと眺めてしまい、こちらを見つめる真島の視線にやっと気づいた。少し首を傾げて、覗き込むように不躾な好奇心を浴びせている。
視線の真意を図りかねて問いかけようと口を開いた、その隙を縫うように、真島の手がこちらの口元に伸びてくる。唇に挟んでいた煙草を器用にさらっていく指がスローモーションに見えた。革手袋についた真新しい傷は多分、この間の喧嘩のものだ。
煙草を攫った指はそのまま真島の口元へと帰り、今まで俺の口に収まっていたフィルターは、真島の唇に差し込まれている。自然に流れていく動きからどうしても目が離せなかった。金縛りにでも遭ったように、指の一本も動かせない。声も出せない。俺の煙草を吸い込む真島を見つめた。瞼が伏せられ、普段は目立たない睫毛が焚き火の炎にちらちら揺れる。眼差しはなぜか科学者のような真剣さをたたえている。瞼を完全に伏せて味わうように深く息をついた。口の端から細く煙が漏れている。
再び煙草が真島の指に挟まれたと思ったら、すとん、とそれを俺の口に差し込む。返された。吸い慣れた味の中に、僅かに真島が漂わせる匂いが混ざる。
「……なんだよ」
金縛りから解放され、やっとのことで絞り出した一言は、幸いにも震えていたりなどはしなかった。目の前の男はすいっと片方だけの目を細める。焚き火に向けていない右目は暗く灯されているが、どことなく優しい色合いをしていると思った。
「ん、桐生チャンの味はどんなんやろなー、と思って」
薄く開かれて弧を描いた唇から舌が覗いている。当たり前だが二股に分かれていたりはしない。同じ人間のはずなのに、真島がその胸元に抱える白蛇のような、底なしの食えなさを感じた。
直後、真島によって発された「ふああ〜」という気の抜けた欠伸によって、空気が完全に弛緩する。
「なんや眠なってきた。帰って寝るわ」
あまりに唐突な展開に一言も発せないでいるこちらに目もくれず、あっという間に公園から歩き去った真島は振り向かずに片手だけを挙げて、「ほな」とだけ言った。やっぱり一瞥もしないまま、その背は見えなくなる。
真島のいなくなった方向の薄明かりを眺めて、ドラム缶に吸いさしを放り投げる。半ばまで吸われた煙草は炎に包まれ、姿を消した。煙草が収まっていた唇がじんじんと痺れる。
「読めねえなあ……」
なんの勝負もしていなかったはずなのに、下手すると喧嘩よりも強く敗北感を味わわされた気がする。
ともすればぐらりと来そうな熱さをぐっとこらえた。焚き火の熱にじりじりと頬を焼かれた、のだと思う。
難しい人(冴島の話をする真と西田)
「親父は、冴島の叔父貴の他の兄弟のことどう思っていらっしゃるんですか」
扉を一枚隔てて、少し音量を落としたジュウジュウと肉の焼ける音と、途切れることのない賑やかな声が響いてくる。
馴染みの焼肉屋の一角。個室として設えられたそこで、自分の親父――カタギ風に言うならば上司にあたる人と、面と向かって座っている。見る者が見れば萎縮しそうな光景であるし、自分も目の前の人物に気圧されることは多々あるが、こうして二人きりで食事をすることは一度や二度ではない。少なくとも他の組員よりは上手くやれている、と思う。
正面に座って網の上の肉を弄くり回しては俺の皿に適当にぽいぽい投げ込んでいた親父は、今は片方だけの目を細めて、怪訝そうな顔でこちらを覗き込んでいる。並の人間であれば半殺しを覚悟するかもしれない顔つきであるが、これもやはり慣れたもので、少なくとも殴りかかるような機嫌ではないはずだ。あまりびくびくし過ぎても親父の機嫌を損ねる。あえて平然とした素振りで肉と米を一緒に口へと運んだ。
「お前、たまーに意味わからんこと聞きよるなあ」
「そうですかね……」
なんとも言えない顔つきのまま口を開いた親父は、返答ともとれるようなとれないような言葉を吐き出した。質問した自分としてはあまり変わったことを聞いたように思っていなかったが、そう言われると自信がなくなってくる。「答えたくなければ、大丈夫ですので」と言うと、「別にええけど」と返ってきた。今日はちょっと機嫌が良さそうだ。
「まあ、聞いたことはあるけどな」
それだけ言って、目線を斜め上に向けて閉口する。言葉を探しているようだ。言いあぐねているというよりは、ピンと来ていないらしい。
「他の兄弟分……みたいなのって、嫌……だったりしないんですか」
ぼんやりとした質問にイライラし始めた様子だったので、説明を付け足す。さすがにこのようなことをはっきり聞くのは躊躇ったが、主旨を理解できた親父は得心がいったのか、若干すっきりした顔に変わる。そしてすぐに「アホくさ」とでも言いたげな表情を浮かべた。よく動く表情筋だ。意外にわかりやすい、と思うことが結構ある。
「西田お前……俺がそない小さい男に見えとったんか? アホらし」
怒りよりは興が削がれたという風体だ。親父に認められていたい自分としては、こういう突き放したような顔が一番心に来る。若干のダメージを負いながら「そういうわけではないんですが……」と絞り出せば、眉間に皺を寄せたまま親父が手元のビールを一口煽った。
「親父にとってはたった一人の兄弟分じゃないですか……何か思うところくらいはあるのかな、と」
苦しい言い訳のように言葉を繋げると、自分を貶めるような意味の質問でないことを納得したのか、ぎゅっと絞られていた眉間が少し緩んだ。理不尽な行動の多い親父だが、落ち着いて話すときには敏い面がよく表れると思う。
「思うところも何も、アイツ元々そういう奴やで」
親父は網の端で黒焦げになっていたホルモンを拾って躊躇いなく口に運ぶ。親父に黒焦げを食わせてしまったことを焦る俺と裏腹に、「うま」と小さく声をあげて咀嚼している。
「懐に入れたが最後、何がなんでも面倒見るっちゅー正真正銘のアホやねん。馬鹿正直で絶対曲げへんしな」
愚痴る口調ではあるものの、遠くを見る目線には慈しむような丸さを含んでいる。おセンチな親父を見ているときにはいつも、なんと声をかけたらいいかわからない。押し黙って烏龍茶を流し込むことで続きを促す。
「兄弟作ることがアイツの幸せなんやったらそれが一番ええ。俺に与えられん幸せを他の兄弟分が持っとるんやったら、そいつと一緒におった方がええねん。俺はアイツに、なーんもできひんかったからな」
言葉だけ聞けば自嘲気味なのに、目の前の人はいっそ爽やかなほど屈託なく笑みを浮かべて頬杖をつく。自分の予想する感情と実際に受ける印象が乖離してきた。桐生の叔父貴に「読めない」と評される親父は、他の人よりも長めに供をしている自分を以てしても、やはり読めないと思う。
「…………」
「アイツの幸せのためにちいとばかり手助けしたろ思てるけど、俺にできるもんも限られとるしな。アイツはもっと良い思いせなあかんねん」
「わかるか?」とダメ押ししてきた親父を、どういう顔で迎えればいいかわからない。もちろん返答も見つかっておらず、烏龍茶が減るばかりだ。そんな自分を気にもしていない親父はメニューを開いてデザート欄などを見ている。多分今日の締めはオレンジシャーベットか。
正直に言うと、親父の言い分には納得がいっていない。親父と冴島の叔父貴の間にあったことは噂程度の情報しか知らないが、冴島の叔父貴にとってのこの人は、もっと大きな存在で、もっと自惚れてもいいほどに、替えのきかない兄弟であるはずだ。叔父貴とは短い付き合いの自分でもそう思うのだ、もっと長くお互いを知っている親父が、そのことを察せないとは思えない。
子供じみているほどに傍若無人で威風堂々と振る舞う割には、親父にはあまり独占欲のようなものが感じられない。好きなものはとことん追いかけるほど執着するくせに、自分の手から離れることそのものには昏い感情を見せない。潔いと言ってしまえばそれまでだが、読めないちぐはぐさが、側近(と勝手に思っている)としての自分をやきもきさせる。もっと理解できれば、もっと的確にサポートできるだろうに。彼自身も意識していないような、得ることを放棄したような小さな幸福をその手に握らせることもできるかもしれないのに。
「お前、アイツにいらんこと言うなよ」
いつの間にか正面を向いていた隻眼が、凪いだ水面のごとき怜悧な視線を投げつけてくる。まるでこちらの心情を読んでいるようなタイミングで、虚を突かれた心臓がぎゅっと縮まった。しかし、研ぎ澄まされた無表情がさっと鳴りを潜め、ばつが悪そうな苦笑が顔を覗かせる。
「これ以上大事にされたないねん」
思わず「はあ」と声が漏れて、それきりこの話題は終わりになった様子だ。親父は二つのメニューの間で指を往復させながらお決まりの歌を口ずさんでいる。
最後に告げた言葉とその表情の意味は測りかねている。瞳の奥に少しの怯えと後悔が揺らめいていたのも、読めないのに明け透けな態度も。まだまだ補佐として未熟であることを痛感したが、冴島の叔父貴に告げ口して殴られる役割は、やはり自分にしかできないことだろうと思うのだ。そのときに浮かぶ顔によって理解を深めることもまた、自分にとってはきっと必要だ。この人に不要であったとしても。
最後にメニュー上で止まった指はティラミスを指していた。店員を呼びつけて「宇治金時氷ひとつ頼むわ」と注文する親父を見ながら、やっぱり理解なんてできないかもしれないな……と思った。