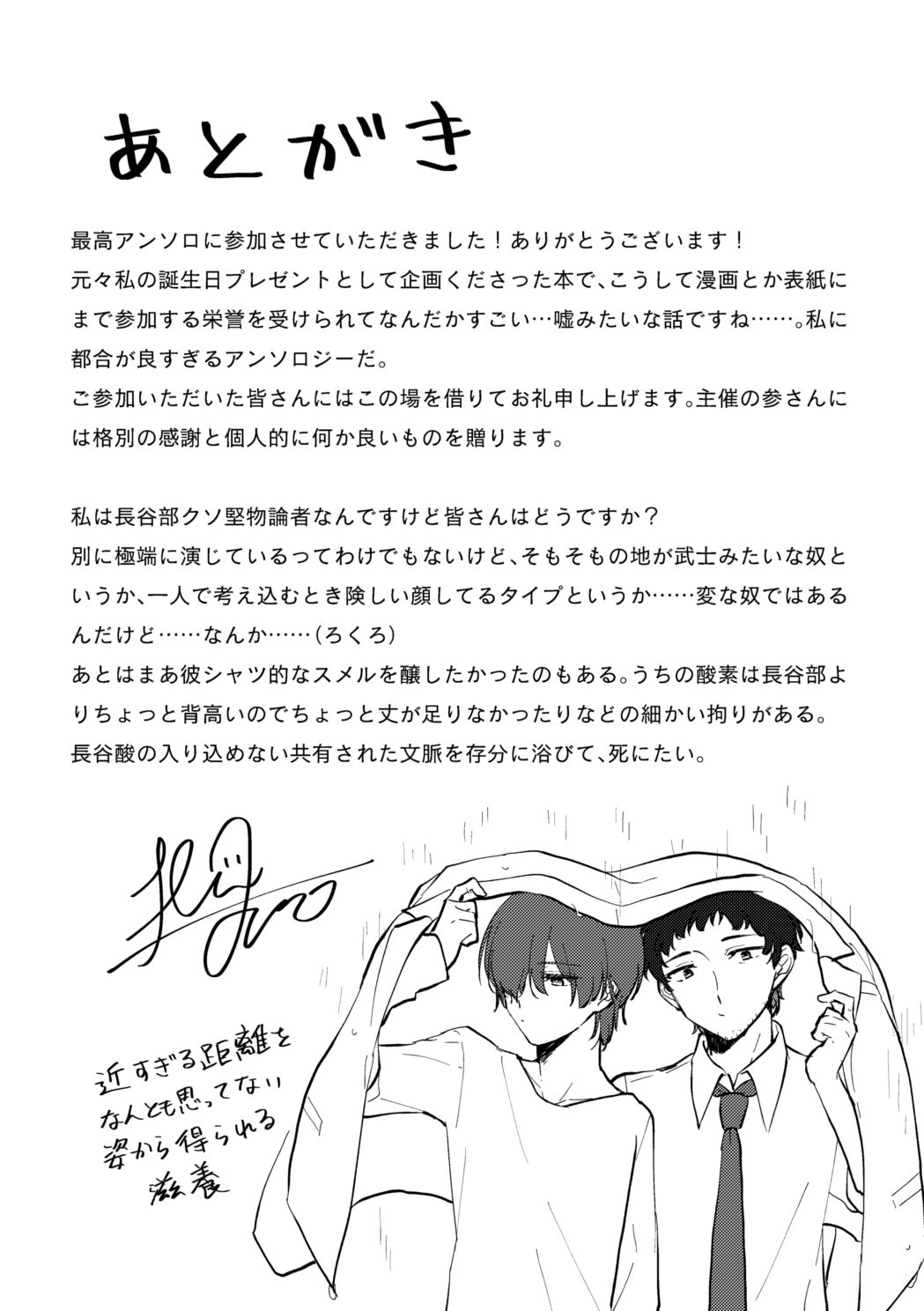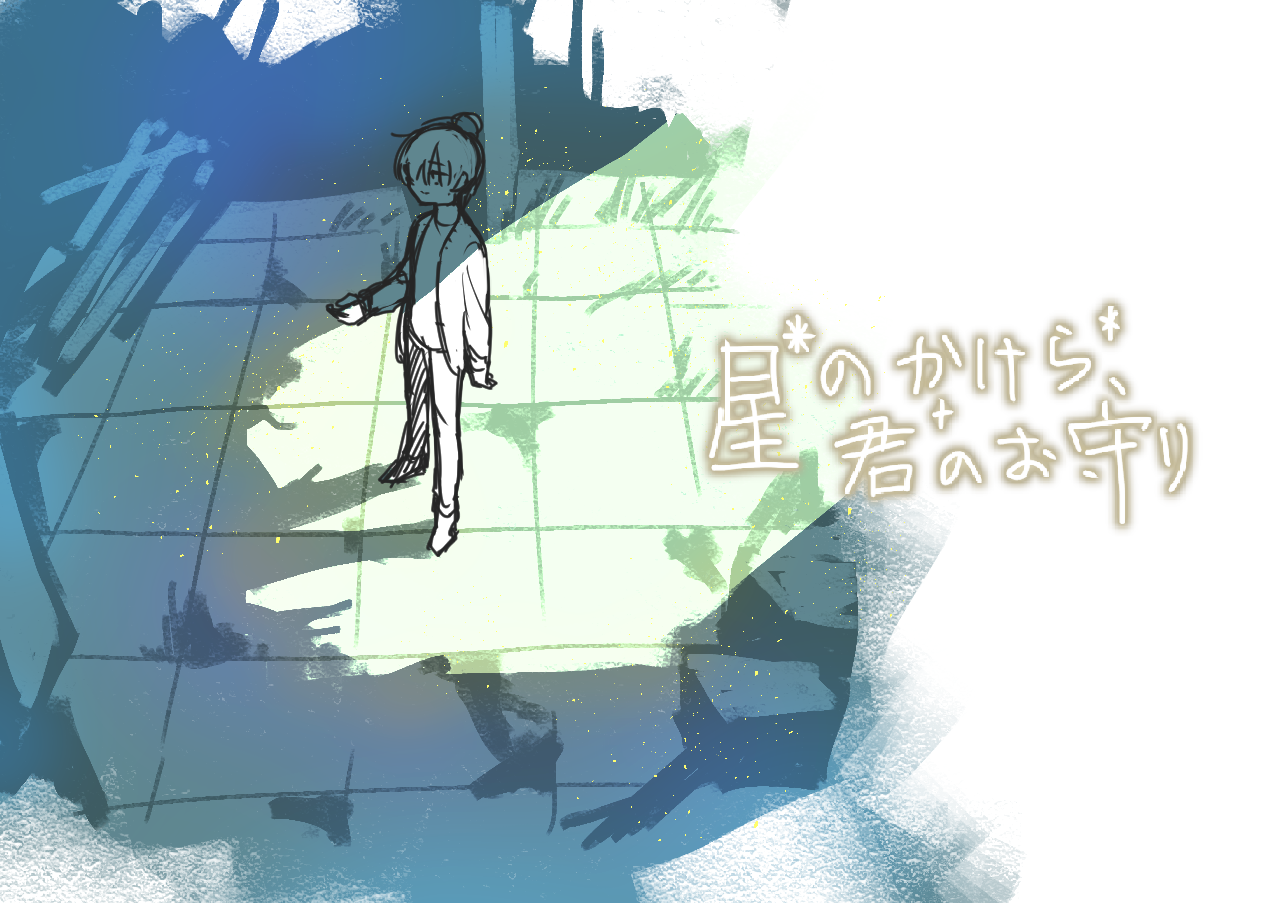
別タブで起動します
男主人公×酸素
ギャルゲーっぽい感じに作ったノベルゲーです。ブラウザでプレイできます。
一応スマホでも動きますが読み込みが長めです。
現在は体験版のみの公開となっています。
テキスト版もあります
読み上げ機能ご使用の方、翻訳が必要な方、ゲーム不可環境だったり苦手な方など向け
※名前変更機能はありません。一部演出やCGが省略されています。ご了承ください。
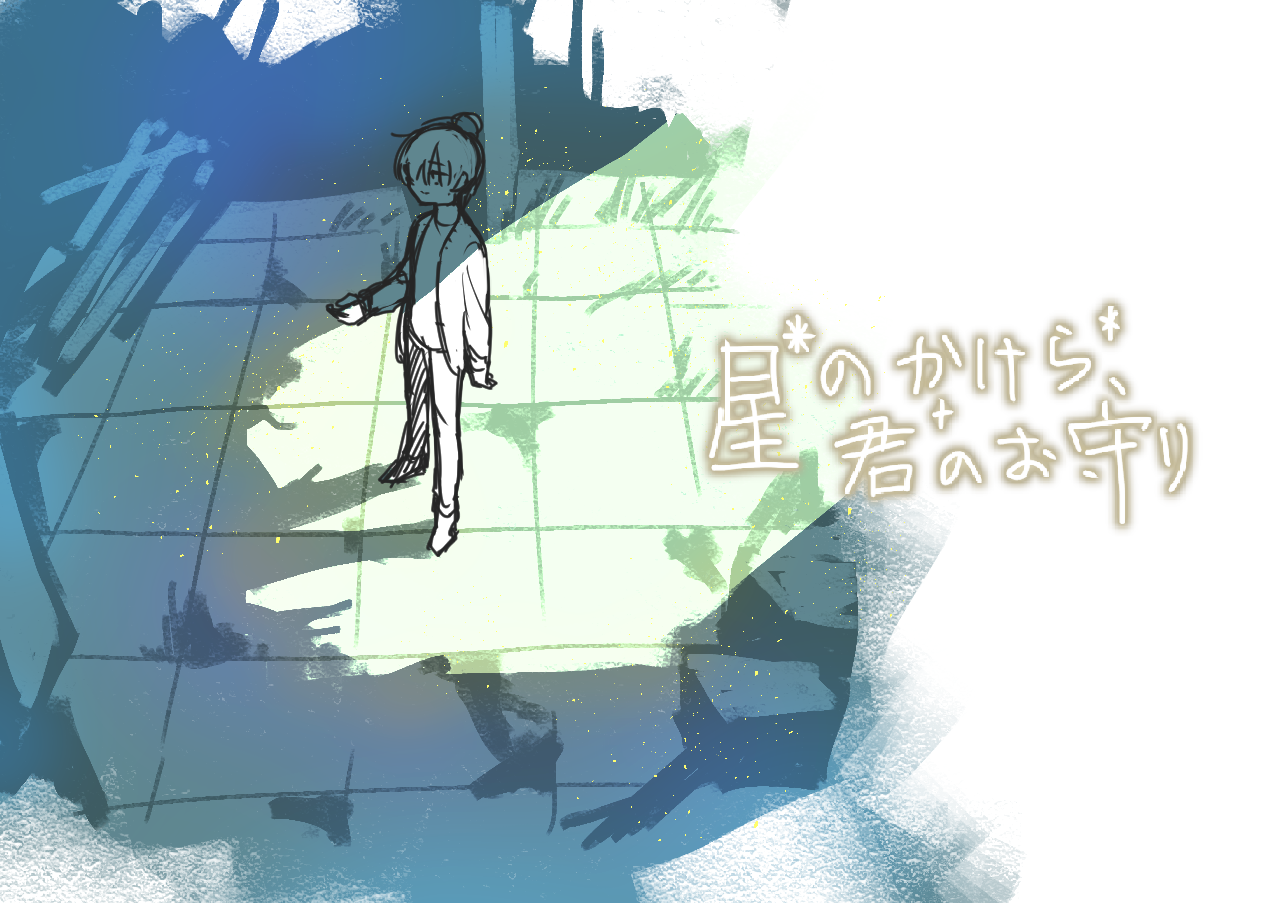
別タブで起動します
男主人公×酸素
ギャルゲーっぽい感じに作ったノベルゲーです。ブラウザでプレイできます。
一応スマホでも動きますが読み込みが長めです。
現在は体験版のみの公開となっています。
テキスト版もあります
読み上げ機能ご使用の方、翻訳が必要な方、ゲーム不可環境だったり苦手な方など向け
※名前変更機能はありません。一部演出やCGが省略されています。ご了承ください。
テキスト版になります。
BGM、SE、演出、一部CG、立ち絵が省略されています。ご了承ください。
うららかな春の陽気が全身を包む。
よく晴れた朝、見慣れた通勤ルート、早朝で人気のない街角、俺の気分はというと……
宮坂誠「はあ……」
思わずため息が漏れてしまうほど最悪だった。
なんというか、ここ最近不運続きだ。今朝だって――
宮坂誠「……ん?」
視界の端に何かを捉えてそちらを向けば、
???「…………」
誰もいなかったはずの道に、一人立っている。
宮坂誠(男……か?)
前髪が長くて、痩せぎすで、特徴らしい特徴も存在感もない、そういう人物がこちらをじっと見ている。
宮坂誠(なんか、別に俺のことを見ているわけじゃないような……)
視線は交わってるはずなのに、なぜかそんなことを思った。
???「……」
その男は何も言わず交わった視線を解くと、すぐそこの曲がり角の向こうに消えていってしまった。
宮坂誠「幽霊とか?」
自分自身の馬鹿げた呟きに、気のない苦笑を漏らして再び歩き出した。
俺の不運は、あの幽霊のせいだったりして。
~職場~
宮坂誠「おはようございまーす」
西条「おはよう」
早朝ゆえほとんど人のいないオフィスに、先輩社員の西条さんが座っている。
西条「今日は災難だったわね」
宮坂誠「あはは……まあ慣れっこですけど」
苦笑いしながら西条さんが労ってくれる。
本来今日の早番は同僚の坂本が担当するはずだったが、
深夜と早朝の間くらいの時間に体調不良で代わってほしいという連絡が来た。
断れない性格であることを見透かされているのか、こういうお願い事が俺の元にはよく集まってくる。
宮坂誠(でもなあ……申し訳なさそうな声を聞くとどうしても……)
自分の押しの弱さに辟易した気持ちをため息に乗せる。
西条「それにしても、最近の宮坂くん、不運続きじゃない?昨日は突然椅子が壊れたり、一昨日は取引先に物失くされたり……」
宮坂誠「それだけじゃないですよ」
西条「え」
宮坂誠「ここ一週間で、車に水たまりの水を引っ掛けられることをはじめ、ケータイを水没させる、コンセントに引っかかって派手に転ぶ、飲み物を手帳にこぼす、キャッチに付きまとわれる、使う電車が全部遅延する、以下省略」
西条「予想の2倍以上ね……」
宮坂誠「なんか憑いてるんじゃないかとお祓いもしてみたんですけど、変わらなくて……
単に星のめぐりが悪い、とかなんですかね」
西条「私からはなんとも言えないけど……案外、誰かの仕業だったりして」
宮坂誠「無茶ですよ。神様じゃあるまいし」
あはは、とお互いに曖昧な笑いをこぼす。
時間が来たため業務に取り掛かると、相変わらずいくつかのアクシデントを抱えながら、
退勤時間まで過ぎていった。
〜退勤後〜
定時を少し過ぎた頃、まばらに人が行き交う街をとぼとぼ歩く。
閑散期だから早めに帰れるとはいえ、仕事のあとはやはり疲れる……。
家に帰ってゆっくりしよう、そう思ったとき。
???「…………」
目の前で、今朝の男がこちらを見ていた。
しかも、朝の遠巻きさとは比較にならないほど近く、人一人分程度空いた先に。
宮坂誠「わぁっ!?」
気配もなく突然正面に現れた男に、思わず俺は後ずさる。
男は何も言わず、俺の反応にも無関心みたいだ。
ただ何かを言いたそうにこちらを見ている……気がする。
宮坂誠「えっと、朝も会いましたよね?」
???「…………」
宮坂誠「俺になんか用ですか?」
得体の知れない人物を刺激しないよう、当たり障りのない会話を投げる。
実際のところ、華奢で覇気のないこの男にまったく脅威を感じてはいないけど、用心するに越したことはない。
???「……」
男はずっと押し黙っている。
もしかしてストーカーとか……?と訝しみはじめたころ、ようやっと男は口を開いた。
???「君の……その不運は、本来僕の操作なしには起き得なかったものだ…………」
見た目通り、陰気なぼそぼそ声で空気が抜けるように喋る。
なんだって?なんでこの男は、俺の不運続きを知っているんだ?
宮坂誠(まさかマジでストーカー……)
ぞっとしないな、と思いはしたが、ストーカー説も半信半疑だった。
ギラついた執着みたいなのを一切感じないし、俺に話しかけてくる雰囲気も警戒するようなものに感じない。
それに――
宮坂誠(なんか……申し訳ない、みたいな……?)
そんな風な空気をわずかに感じて、毒気を抜かれている。
宮坂誠「あのー……なんかわかんないですけど、要するに俺の不運はあなたのせい、ってことですか?」
???「そう捉えても差し支えない……。これらの事象はすべて君の運命が内包していたものだが……確定しているわけではなかった……。それを絡ませ、固定したのは……僕による影響が大きい……」
宮坂誠「そんな馬鹿な。神様や仏様じゃあるまいし」
???「神、ね……僕ができることなど、大したものではない……」
彼の言うことはちんぷんかんぷんだし、なんだか占い師とかが言ってそうな現実味のない話だ。
俺の運命を操作した?とか言ってるのか?
そんなバカな、今まで人為的に不運を起こしていたのを誤魔化している、とか考えたけど、
それも陰謀論くさくなってしまう。
話がうまく飲み込めないが、とりあえず――
宮坂誠「よ、よくわかんないですけど……俺は別に、大丈夫なんで。大したことなかったし」
なんだかいたたまれなくて、この目の前のよくわからない彼を許してしまった。
相手が誰であれ、あまり元気のない姿を見ていたくはない。
???「…………」
彼がわずかに驚いた顔をしたので、珍しいものを見た気持ちになる。
???「あまり……人が好すぎるのも考えものだな……」
今度は困った顔で少し笑う。
得体が知れないと思っていたけど、案外普通の人かもしれないな。
俺も曖昧な苦笑いで頭を掻く。
???「ただ……」
宮坂誠「え?」
???「この運命がどこまで影響しているか把握しきれていない……近いうちに、君に更なる不遇が降りかかるかもしれない……」
宮坂誠「そ、それってどのくらい……」
???「最悪、命を落とす」
無表情に(ちょっとだけばつが悪そうに)告げられた宣告があまりにも現実味がなくて、
他人事みたいな乾いた笑いが出る。
???「だから……これからしばらく、君と会うことにしよう。……不運が近づけば、ある程度の対処はできる……」
混乱している間に、不可思議な話は不思議な方向にまとまっているみたいだ。
少し下にある頭から覗く瞳が俺のことを見透かすようで、それがなぜか嬉しかったからだろうか。
だから――
宮坂誠「じゃあ、その、明日帰り道に、そこのカフェで……」
約束をしてしまった。
宮坂誠「あ、そうだ。俺、宮坂誠です」
ご丁寧に名まで名乗って。
柊「……オキシジェンだ。柊、でも構わない……」
柊は意外そうな、呆気にとられたような声色を乗せている。
宮坂誠(もしかしてこの反応、レアなんじゃないかな)
不運続きの俺に、久々に舞い込んできた幸運なのかもしれなかった。
〜翌日〜
宮坂誠(来ちゃったなあ……)
今日の仕事を終えて帰り道、結局俺は昨日約束したカフェの前に来ている。
あんな妙な約束、帰り道を変えるなりすればなんとかなるかもしれないのに、我ながら律儀だと思う。
宮坂誠(柊さんのことも、気になるといえば気になるし……)
死にたくもないし。
店員「いらっしゃいませ!何名様ですか?」
宮坂誠「あー……っと、多分連れが来てると思うんですが……」
きょろきょろと見回すと、一番奥の窓際にその姿を見つけた。

宮坂誠(いつから待ってたんだろう……)
柊はその席に馴染んでいて、あまりに自然だったから、ずっとそこに住んでいるみたいだ。
すごく待たせたかもしれない、という思いに駆られて、急いでテーブルに近寄る。
宮坂誠「お待たせしました」
柊「……問題ない……」
向かいに座ってコーヒーを注文する。
柊は窓の外を見ているが、なぜかこちらを無視している風ではないような気がする。
宮坂誠「何見てるんですか?」
柊「……知りたいか?」

ぎく。
柊の視線があまりになんというか、踏み込んではいけない領域に思えて、
俺は少し身体を強張らせる。

宮坂誠(……あれ?雰囲気が柔らかくなった)
柊「今日は……人通りが多いからな……。何かあるのかと探していた……」
さっきのひりつくような緊張が嘘のように、無難な答えが返ってきた。
宮坂誠(いや、なんとなくはぐらかされた気もする……)
ちょっと悔しいかもしれない。
宮坂誠「この辺りでドラマ撮ってるみたいですよ。それのスタッフとか、野次馬じゃないですかね」
柊「ああ、あの……」
宮坂誠「知ってるんですか?」
意外だ。
いや、失礼かもしれないが、目の前のこの男と、俗っぽい知識が妙に似つかわしくない。
柊「知人が参加していた……という程度だ……」
宮坂誠「へえ〜!芸能人のお知り合いが!」
更に意外だ。もうこの人に意外なことなどないのかもしれない。
宮坂誠「……」
柊「…………」
…………………
宮坂誠「それで……俺って具体的に何すればいいんですかね?」
沈黙に耐えきれなくて、ここで会った目的を改めて確認する。
しかし、柊はゆっくりと首を振る。
柊「君自体は……何もすることはない」
宮坂誠「そ、そうなんですか?」
柊「この運命を……君が認識することは難しい……。君と会いながら、僕が少しずつ絡まった因果を解く……それが目的だ」
柊は手近にあったストローの袋を絡ませている。説明のつもりなのだろう。
柊「本来……運命と、それに付随する事象に……明確な指向性は存在しない……。ゆえに、運命の渦中にある者がどう感じていようと……それが運命に作用することはほとんど、ない。……しかし、君が望んだ末の行動は、糸の因果にも組み込まれる。その結果、君の意図しない方向にばかり物事が運ぶということも、起こり得るのだろう……。このような運命の絡まり方は……珍しいが……」
宮坂誠「……」
柊「…………」
宮坂誠「………………」
柊「……つまり、やること成すこと裏目に出る、ということだ」
宮坂誠「なるほど」
要約してもらうまでさっぱり意味がわからなかったが、こうして聞くと、
柊のこの回りくどい言い回しというのは、彼なりの理解の仕方なのかもしれない気もしてくる。
宮坂誠(さっぱりわかんないけど)
絡ませたりほどいたりしていたストローの袋を置いて、柊は手元のアイスコーヒーを啜る。
宮坂誠「そういえば注文したコーヒーが来ないな。」
店員「お客様、大変申し訳ありません!先ほどコーヒーメーカーが故障してしまって……復旧までしばらくお待ち頂いてよろしいですか?」
宮坂誠「……注文キャンセルで、ジンジャーエールでもください。」
店員はぺこぺこしながら慌てて厨房に駆けていった。
宮坂誠「できれば、早めになんとかなるとありがたいです……。」
柊「……善処しよう…………。」
それから毎日、俺は柊とこのカフェでお茶をしている。
てっきり儀式だかお祓いだかみたいな、神秘的なものを想像していたんだけど、柊は特に目立って何もせず、俺と話しながらコーヒーを飲んでるだけだ。

宮坂誠「うーん……。」
柊「僕が本当に君の不運を解消してくれるか不安、か……?」
どきり。
かすかに唸った俺の声だけで、全部見透かされてしまった。
いや、これまでにも俺の考えが筒抜けだったことは度々あるから、俺がわかりやすいだけかもしれない。
それはそれで凹むけど。
宮坂誠「だ、だって……運命、とか言ってたので。なんかそれっぽい儀式とかしないのかなーって。」
柊「儀式、その形式には意味はない……。曖昧な概念、目に見えない願いを……その場で共有するためのものだ……。」
宮坂誠「じゃあ、俺に共有してくれてもいいんじゃ……。」
柊「したところで、君の不遇は晴れはしない……。これは、不安や想いとは関係のない事象だからだ。」
宮坂誠「うぐぐ。」
柊「それに……僕が本当に君の不運を解消しようとしまいと、君には他に頼れるところもない……。」
宮坂誠「顧客満足度のことも考えてくださいよ。」
柊「……追加料金だ。」

宮坂誠「初めて会ったときはあんなに殊勝だったのに……。」
そう。
柊は本来の調子を取り戻しているのか、あのちょっと落ち込んだ姿は鳴りを潜め、
今も悪戯っぽくこちらを見ている。
宮坂誠「こっちが本性か……。」
柊「どうかな。」
俺をからかってるときの柊は楽しそうだ。
からかわれてる当人の俺はというと、そんなに悪い気はしていないのが困りものだ。
落ち込まれるよりはよっぽどいいし、俺への悪意みたいなのは感じない。
ここ数日話してて、不思議な物言いをする以外は、これといって怪しい人物でないこともわかる。
柊は浮世離れした雰囲気と裏腹に、ひどく明け透けだと思う。
どんな人も持ってるはずの見栄とか建前がなくて、他の誰にも混ざることがない。
宮坂誠「柊……って、」
柊「…………。」
初めて呼び捨てにしてみても、ぴくりとも反応しない。
これはちょっと寂しいけど、拒否されなかったのは幸いか。
宮坂誠「なんで俺のこと助けようとしてくれるの?運命……だかなんだかのせいなら、柊のせいって誰にもわからないのに。あんたも実際お人好しとゆーか、真面目とゆーか……。」
柊「……残念ながら、君の思うような人間ではない……。」
僕は僕で気になることがあるから……こうして君と関わっている。
いわばついで、だ。
宮坂誠「ついででもなんでも、俺は助かってるから。」
柊「…………君も大概変わっているよ。」

少しの苦味と楽しげな空気を含んだ微笑みは、まだ見たことない表情だった。
宮坂誠「そういえば、なんでこのカフェ集合なんだ?なんか……地脈、みたいなものとか?」
柊「いや、別にどこでも変わらないが……。」
宮坂誠「えっ!?」
柊「不遇の運命は、君を中心に形成されている……。君がいる場所ならば……どこにいても同じだ。」
宮坂誠「それを早く言ってくれ……。」
柊「聞かれなかったからな……。」
なんでこんなに肩を落としてるのかと言えば、今日が休日だからだ。
自分の不運を解消するためならカフェに籠もりっきりも仕方ないと思ってたのに……。
あと、カフェの人たちにも申し訳ない。
宮坂誠「まだ昼になったばかり……よし!」
おもむろに立ち上がった俺を、柊の視線が追う。
宮坂誠「追加料金としてコーヒー代奢るから、俺の行きたいとこに付き合ってほしい!」
柊「…………まあ、構わないが。」
そんな調子で、俺と柊のお出かけ休日が幕を上げるのである。
宮坂誠「なんでちょっと笑ってんの?」
柊「いや……知人を思い出す強引さで……少し懐かしい。」
〜街〜
柊「それで……、どこに行きたい?」
宮坂誠「行きたい場所は……」
宮坂誠「映画館、かな。」
柊「映画?」
宮坂誠「うん。今月で公開終わりそうな映画があって。見ておきたいと思ってたんだ。」
柊「君が行きたいというなら、付き合おう……。」
〜映画館〜
宮坂誠「あった!席も空いてるみたいだ。よかった〜。」
柊「これ、か……。」
俺が指しているのは、絶賛公開中のホラー映画「獄島」だ。
主人公はとある小さな島に、サークルで旅行に来た大学生。その島では奇妙な風習が根付いており、次々と凄惨な死を遂げる仲間たち。
やがて主人公は島を覆う巨大な陰謀に巻き込まれ……という内容らしい。
一見すると要素を詰め込んだB級映画に見える宣伝だったが、『意外に骨太』『宣伝で損してる』などSNSで意外な評判を呼んでいる。
宮坂誠「ホラー大丈夫だった?」
柊「問題ないが……。」
柊はほんのわずかだが訝しげな顔をしている。このポスターを見るとそりゃそうだろうなと思う。サメいるし。
宮坂誠「ま、まあ割と面白いらしいから!楽しめると思うよ!」
慌てて弁解のような言葉をかけると、柊はいつもの何も気にしてない顔に戻る。
まずは飲み物でも買おうと発券機に背を向け、歩き出したそのときだった。
???「おいアンタ!その足どけろ!」
男性の大声が響いて、思わず俺は下を向いて足をどける。
すると、俺の足があった場所には映画のチケットが落ちていた。
男性「どうしてくれんだ!汚れちまっただろ!」
大きな声の方向には、こちらを睨みつけているおじさんがいる。
宮坂誠「ご、ごめんなさい、気づかなくて……!弁償します!」
突然の険悪な人物に焦ってしまって、わけもわからず謝った。
男性「俺はこの席の券が欲しかったんだよ!弁償で済むか!」
宮坂誠「じゃ、じゃあスタッフの方に交換してもらえないか聞いてきますので……。」
男性「それじゃあ俺の気が収まらねえだろうが!誠意見せてもらおうか、誠意。」
おじさんの剣幕は留まるところを知らない。こちらに非があるとは言え、こんなに怒ることないだろ……と思い始めた。そのとき。
柊「あんたのその、怒り……それは僕たちとは無関係に引き起こされている……。」

怒号が響いていた空間に、場違いなほど静かな囁きが落ちた。
しかしその呟きは苛立ちの隙間を縫うように発せられたのか、おじさんは思わずしんとして柊に目を向けている。
柊は俺より一歩前に出て、おじさんを真っ直ぐ見つめる。なんの迫力もない声なのに、おじさんは気圧されて少しのけぞった。
柊「あんたには、自分ではどうにもならないことがのしかかっている……。それを解消する術がないことも、わかっているだろう……。」
柊はいっそ素っ気ないと感じるくらい、淡々とした声色で突き放すように言う。
あくまでずっと平静な柊と対称的に、おじさんの顔は引きつって赤く染まっていく。
この表情を知っている。いわゆる”図星”だ。
男性「テメエッ!!適当なこと言いやがって!!!」
おじさんは激昂して柊に掴みかかった。柊は抵抗らしい抵抗もなく、腕の辺りをキツく握りしめられる。

宮坂誠「や、やめてください!」
俺は思わずおじさんを引き剥がして、2人の間に入った。

男性「うるせえ!!!」
おじさんは勢いが収まらないのか、引き剥がされた腕の勢いをそのままに、俺の顔面めがけて振りかぶる。
宮坂誠「ッ!!!」

痛い。武道の覚えなんて全然ないから、避けられもしなかった。
おじさんも暴力に慣れてるわけじゃないのか、当たりどころは少し外れてる気もするけど、それでも顔面に当たれば痛い。頬を押さえてよろける。
柊「…………。」
柊が一瞬こちらを見て、またおじさんに向き直った。
柊「世界への鬱憤を晴らしたいのなら……この程度でどうにかできるわけがない……。己の無力を知りながら、前にも後ろにも進めず……もがくしかないのだろう……。」

柊はさっきと同じような内容を喋っているみたいだけど、今度はなんだか雰囲気が変わっている気がする。
宮坂誠(脅している……?)
男性「な、なんだと……。」
柊「そうだな、お前は……この先もその暗闇を抱えたまま、世界を変えることも、敵に回ることもできまい……。」
糸はこれ以上どこにも繋がらず、切れていくだけ……。
男性「う、うううう……!」
目に見えておじさんは憔悴していく。
ひたひたと迫るような柊の声は、確実におじさんを追い詰めている。
柊「……相応しい場所へと帰るがいい。この運命は、ここで終わった。」
柊が言い終わるか終わらないかというところで、おじさんはバタバタという足音とともに走り去ってしまった。
事態から取り残された俺は、ぽかんとおじさんの方を見ている。
宮坂誠「い、今のはなんだったんだ……柊?」
傍らにいる柊に話しかけたはずが、きょろきょろと見回してもその姿がない。
騒ぎを聞きつけて遠巻きに見ていた客がいつの間にか取り囲んでいた。
宮坂誠「う、うわ……!どこ行ったんだよ~……!」
負傷したのに置いていかれたことに若干心を痛めつつ、人混みをかき分けて静かな空間に向かう。
少し遅れてスタッフが走ってきて周りの人に事情を聞いているようだ。見つかったら面倒かもしれない。
宮坂誠「うぅわっ!?」
頬にあたるキンと冷えた感覚。
振り向けば、ドリンクのカップを片手に持った柊が立っていた。
宮坂誠「い、いつの間に……ていうかどこに行ってたんだ!」
柊「これで冷やすといい。」

俺の言葉を聞いてるのか聞いてないのか、また頬にカップを押し付けてくる。
じんじんとした熱がカップに吸い込まれていくようで気持ちいい。
宮坂誠「もしかして……これを買いに行ってくれたのか?」
特に肯定も否定もせず黙っている柊からは、これといった主張は読み取れないが……
どことなく「だからどうした」とでも言いたげな雰囲気がある。気がする。
宮坂誠「お、置いていかれたかと思ったから……ありがとう。」
俺のことにあまり興味のなさそうな柊が気にかけてくれたのが嬉しくて、思わず笑顔が浮かぶ。殴られた頬が引きつって痛い。
宮坂誠「柊は度胸あるんだな。怖そうな人だったのに……。腕に覚えがあるとか?
柊「別に……。あの男にも僕にも、大した力などない……それだけだ。」
宮坂誠「それだけって……。」
柊「僕を庇う必要もなかったはずだ……特に、今の君は何が起こるかわからない……。」
宮坂誠「う。で、でも俺の方が図体がでかいから……。丈夫かと……。」
柊「……勇気がある、ということにしておくか。」

柊がふわりと笑って、珍しい表情に思わずぎくりとする。
この事態も俺の不運が招いたのだろうか。珍しいものが見られるという点では、あながち不幸だけとも……。
柊「滅多な気は起こさない方がいい……。君が真に平穏を取り戻したいと思うなら、な……。」
一転して冷たい空気を纏った柊が、見透かしたように釘を刺す。
宮坂誠「はは、まさか……。」
何に釘を刺されたのかもわからないまま、曖昧に笑った。
柊「ところで……」
宮坂誠「ん?」
柊「目的の映画はもう始まっているようだが。」
宮坂誠「ええっ!?」
映画のチケットと時計を交互に見る。すでに上映開始して10分が経っていた。
宮坂誠「ま、まだ宣伝とかの時間かも……!急げ!」
映画の休日が慌ただしく始まった。
宮坂誠「あ、そうだ。」
柊「?」
宮坂誠「たしかここに……あった。」
俺が取り出した2枚のチケットに柊が目を向ける。券面には「SUGOI AQUARIUM」の名前が書かれている。
宮坂誠「職場の人にチケット貰ったんだけど、今月までで……。せっかくだから、どう?」
言ってしまって、まだ友達とも言っていいのかわからない人を水族館に誘うのってどうなんだ……!?
と思ったけど、今さらナシにするのも不自然かと思い、平静を装うことにした。
柊は俺みたいな葛藤なんてまったくないのか、淀みなく頷く。
柊「君が行きたいなら……。」
ちょっと遠くの場所だから、電車での移動になった。
柊はそんなに喋るタイプじゃないのに、移動時間は苦にならなかった。
〜水族館〜
宮坂誠「わあ〜……結構並んでるなあ。」
水族館にはチケットを購入したい人が列を作っている。
人気の水族館な上に休日だからか、家族連れやカップルがお喋りしながら自分の番を待っている。
先にチケットを持っていた俺たちはまっすぐ入口に向かい、入場することができた。
〜水族館内〜
宮坂誠「おおー。」
水族館の中は薄暗さが神秘的な雰囲気を醸し出している。
宮坂誠「ここ、話題になってたけど来るのは初めてなんだよな。」
柊「そうか……。」
宮坂誠「くらげの水槽が有名らしいよ。順路に沿っていけば見られるかな。」
柊は俺の隣をつかず離れずといった調子で着いてくる。静かなものだが、俺の言葉には相槌を打ってくれるし、
たまに水槽を眺めたりしているから楽しんでると思っておく。
宮坂誠「柊はさ、こういうとこ来るの?」
軽い雑談のつもりで柊に話しかける。
柊はぼんやり光る水槽から視線を外し、こちらを向いた。
柊「いや……自ら来ることは、ないかもな……。」
宮坂誠「仕事が忙しいとか?」
柊「まあ、そんなところだな……。」

柊が自嘲するような顔で苦笑する。
今の仕事が上手く行ってないんだろうか。
そういえば柊がなんの仕事をしているか知らないな、と思ったけどそれを軽率に尋ねるのは憚られた。
柊「長く……自分の使命に縛られすぎて……、久しく休息も忘れていた……。」
宮坂誠「たまには肩の力抜いてもいいんじゃない?世界が終わるわけじゃないしさ。」
柊「…………。」

柊がきょとんとした顔で固まっている。やっぱり急に話の規模を大きくしたのが意味わかんなかったのか……?
よく考えたら自分の仕事を些細なことだと言われたようなものだから、不快に思ったかもしれない。
そんなつもりじゃない、と言いかけたところで――
柊「……ふ、はは。そうだな……君の言うとおりかもしれない。」

柊が笑った。それも今までにないくらい明るく。
思わず柊の方を凝視したあと、見てはいけないものを見た気持ちがして目をそらす。

宮坂誠「そ、そうだよ。」
俺なんてさ、取るに足らない事ばっかりしてるから、あんまり深刻に考えすぎないようにしてるんだ。
柊「いいや……、世界は君の思うような”取るに足らなさ”でできている……。君がどのように生きたとしても、それは世界に影響を及ぼし、また及ぼさないことだろう……。自分の起こすこと、世界に起こったこと、在るもの、無いもの……それらすべての認識を操れば、君にだって世界を支配できる。」

宮坂誠「世界を支配……?まさか、大げさな。」
柊「君が君自身を生きることと、世界を支配することは、常に隣合わせだ……。君次第で、世界は如何様にも変わることを、覚えておくといい。」

柊「君の一言で、世界の支配者が1人……安らげたことも。」

柊はそう言うと、別の水槽を見に行ってしまった。
難しいことを言っていたけど、要するに励ましてくれてありがとう、みたいなことを言いたかったのだろうか?
なんとなく細部を省略しすぎた気がするが、柊が穏やかな顔をしていたのが嬉しかったのでよしとしよう。
ふわりと破顔したときの余韻がずっと頬に残ってる気がする。薄暗いからバレてないことを祈った。
〜水族館外観〜
あれからも色々と見回って、お土産売り場を軽く眺めて建物を出れば、空が少しオレンジがかった日の入りになっていた。
宮坂誠「結構広かったから時間かかったな〜。」
柊は目に見えてはしゃいだりしなかったものの、幾分か雰囲気が柔らかくなったように思える。
宮坂誠(俺も楽しめたし、いい休日になった気がするな……)
少しほくほくした気持ちでいると、柊がじっと遠くを見ていた。視線の先は――
宮坂誠「おお、夕日だ……!」
水平線の先に夕日が沈んでいる。水族館が海の近くにあるため、少し歩けば浜辺に辿り着く。
宮坂誠「そうだ、せっかくだし海にも寄っていかないか?春の海って新鮮だしさ。」
柊「…………。いや、まあいいだろう……。」
柊は視線を伏せて考え込んだあと、歯切れ悪く頷いた。
宮坂誠「もしかして時間とかまずかった?」
柊「時間は問題ない……。……こちらの方がマシ、かもしれないしな……。」
柊が口の中でもごもご言っている。
なんとなく珍しいな、と思ったのは、俺にその独り言を聞かせたくなさそうだったからかもしれない。
引っかかりつつも、石で出来た階段を降りれば広い浜辺に辿り着く。水族館ついでに寄ったと思しき人もぱらぱらいるみたいだ。
宮坂誠「やっぱり遠くから見るより絶景だ!」
波打ち際に近づく俺に、柊も着いてくる。
海なんて忙しくてなかなか来られなかったから、年甲斐もなくはしゃいでしまっている。
宮坂誠「へ〜ここの海って結構澄んでるんだな。ほら柊!蟹もいる!」
柊「そうだな……。足元に気をつけないと、濡れるぞ。」
テンションの高い俺を宥めるように苦笑しながら、俺の指差す方を覗き込む柊。
なんだか面倒を見られる子供にでもなった気分で気恥ずかしくて、熱くなる頬を誤魔化しながら笑った。
宮坂誠「は、はい……気をつけます……。ちょっとはしゃぎすぎたかな。」
柊「いいや……、言い方が悪かった。君が気をつけようとそうでなかろうと……。」
宮坂誠「え?」
柊が不穏な言葉を残した一瞬の後、俺たちは異様に跳ね上がった波に頭から包まれる。
当然、つま先までびしょ濡れの二人が出来上がった。
宮坂誠「な、な……なんだ今の波!!!浜辺であんな打ち上がり方しないだろ!」
柊「そうは言ってもしたからな……。」
宮坂誠「不運って物理法則も無視するのか!?」
柊「まあそういうこともあるんだろう……。」
宮坂誠「もしかしてこうなることを知ってたから、ちょっと気まずそうに……?」
柊「いや、以前も言ったように……何が起こるかは僕にはわからない……。ただ、大体の推測くらいは立てられる、というだけだ…。」
宮坂誠「教えてくれれば避けられたかもしれないのに……。」
柊「どこに行っても一定の確率で不遇な目に遭う……。その中ではマシな方だろう、と判断した。しばらくは安全に過ごせるはずだ……。」
宮坂誠「うーん、納得行かないけど……。……あ、」
状況が飲み込めてきて、冷静な頭で改めて柊を見る。

俺のすぐ側にいたから一緒に濡れ鼠になっていて、水を吸って重たくなった衣服が柊の細身を顕にしている。
これはすごく……なんか……
宮坂誠「いやそうじゃなくて!」
柊「……どうした。」
宮坂誠「寒くないのか柊!風邪でも引いたら……あ、俺の上着も濡れてる……。」
上着を貸そうと引っ掴んで、じゅわっと染みた海水の感触に脱力する。
無意味にオロオロしてる俺の様子を見て柊がくすくす笑った。
柊「なぜそこで僕の心配なんだ……。」

宮坂誠「だ、だって……柊って痩せてるし、ちょっと繊細そうというか……。」
柊「ふふ、そう見えるか……。問題ない。僕はこう見えて……案外丈夫なんだ。」
宮坂誠「それは良かったけど……。ああでも、なんで一緒に濡れてるんだよ。わかってるなら柊だけでも避難するとかさ。」
柊「正確なタイミングまでは掴めない……。不運を避けるより、君と過ごすことを選んだというだけだ。」
宮坂誠「な、なにそれ……。」
柊はなんでもないように言うけど、それって結構すごいことじゃないか?
何はともあれ、海岸は風が吹きすさんで、しとどに濡れた肌を撫でていく。
縮こまる俺と対称的に、柊は平然とした顔だ。丈夫だというのは本当かもしれない。
しかし、いつまでも濡れたままでは風邪を引くなんて時間の問題だ――
宮坂誠「俺のうちさ、割と近いから……。」
思わずぽろっと溢れて、段々と尻すぼみになっていく。
宮坂誠(ど、どうなんだろう?この距離感で家に誘うのは変か?でも柊を濡れたまま返すわけにいかないし、一緒に遊んだんだから家に誘うくらい大丈夫なのか?こんな関係性の人ができたことなんてないからわからない……!というか言葉が途中だったから意図もよくわからなかったかも)
という俺の葛藤を知ってか知らずか、柊は俺の言いたいことを汲み取った様子で
柊「そうだな……じゃあ、お言葉に甘えよう。」
と包むように微笑むのだった。
宮坂誠(やっぱり俺の考えてること全部読まれてる気がする……)
下心とか、持ってはいけないのかもしれない。
〜家〜
ドライヤーの轟音に耳をつんざかれながら、全然聞こえないテレビの画面を見つめている。
内容は頭に入ってこない。テレビは円周率とか素数の代わりだ。心を無にするためにある。
なんてことはない普通のワンルーム。
駅からそこそこ、街からも少し離れた住宅街の、ありふれたマンションの3階。
平凡な俺が住むにはおあつらえ向きだ。
落ち着かない原因はといえば――
宮坂誠(柊が、いるんだよな……)
俺の家の、風呂に。
柊ってシャワーとか浴びるんだな、いや浴びるだろなんだと思ってるんだ。
という自己との会話を数十回は繰り返している。
別に、一緒に遊んでた人が濡れたからシャワーを貸してるだけ。そうだよくある話だ。
よくある話だが、相手が柊となると妙にそわそわしてしまう。よくある話とあの神秘的な雰囲気のギャップに戸惑ってるのかもしれない。
そういうことにしておこう。とりあえず人心地つける結論を捻り出してドライヤーを止める。
柊「考え事は済んだか……?」

嘘!落ち着かない!心臓に悪い!
いつの間にか隣に座ってる柊に不意をつかれて、ばくばくとうるさい心臓をなんとか宥めすかす。
宮坂誠「びっっっくりした……いつの間に上がってたんだ。」
柊「……服を借りたが、よかったのか。」
宮坂誠「あ、それは用意してたやつだから、全然……。」
濡れた服は洗濯機の中で回っている。乾燥も一気にできて便利なやつだ。
柊は俺より少し背が小さい(俺がでかい方なだけだが)し、細身だから貸した服の身丈が少しずつ余っている。
なんかこのサイズ感ってあれだな、いわゆる彼シャ……
柊「見すぎだ。」

じっとりとした視線を柊から感じる。いや、むしろ柊がじっとりとした視線を感じていたのか。
慌てて目をそらして弁解する。
宮坂誠「ご、ごめんっ!そんなつもりじゃ!」
柊「どんなつもりだ……。」
ちょっと呆れたように小さくため息をつかれた。
たしかにどんなつもりだったんだ俺は。何を考えようとしたか、慌てたせいで飛んでいってしまった。
柊「……何か淹れよう。勝手に借りるぞ……。」
宮坂誠「え!いや、大丈夫だって。俺がやるよ。」
柊「世話になった礼だ……。悪いようにしない。」

とだけ言って、台所にすたすたと歩み寄る。カウンターキッチンの向こうを、なんとなく気にしてしまう。
申し訳ないが、柊からは生活感みたいなのが感じ取れない。
どこか俗世間から離れた雰囲気があるせいで、もしかしたら家電なんて使ったことないんじゃという気すらする。
そんな俺の心配をよそに、柊はぱたぱたと棚を物色すると、手頃なインスタントコーヒーを見つけ出し、
カウンターに置いていた電気ケトルに水を注いでセットして、その辺のマグカップにコーヒーの粉を測り入れる(目分量で)。
宮坂誠(なんか……フツーだ)
危なっかしいところもなく、拍子抜けするほど普通に、むしろ手際よくコーヒーを仕上げていった。
妙なイメージを持っていた自分が恥ずかしい。
柊「……意外、か?」
2つのマグカップの1つをこちらに差し出しながら、柊は苦笑している。

宮坂誠「実は、ちょっと。ごめん。」
柊「いや、慣れている……。問題ない。」
慣れてるって……柊って誤解されやすい奴なのか?
と思ったが口には出さず、コーヒーを喉に流し込んだ。柊も静かに口を付けている。

2人とも黙ってしまったから、狭い部屋にはテレビの陽気な音だけが響く。
今日は色んなことがあって、俺の不運のせいでこうした状況になってるけど、
裏を返せば不運のおかげでもあるわけで……。
宮坂誠「柊、俺さ……。」
柊「君は、運命というものをどう考える……?」
宮坂誠「え?いや、運命……って」
俺の言葉を遮って、柊は掴みどころのない問いを投げる。
投げられた問いに対応しようとして、自分が何を言おうとしたか忘れてしまった。
宮坂誠「なんか……神様が決めたもの、とか……。あらかじめ決まってる未来みたいなイメージ?」
柊「……そう、イメージだ。運命とは理不尽に、事象の繋がりによって引き起こされるものだが、それもまた一側面に過ぎない……。別の見方をすれば、運命に物語を見出すこともできる……。」

宮坂誠「物語?」
柊「人間が物事を受け入れる際の心の動き……とでも言おうか。事象とは常に発生しているものであり、何かに合わせて動いたり休んだりする性質ではない。しかし……人間は自分の意識する出来事を殊更に取り出し、特別に意味をつける……。それが物語であり、別側面での”運命”とも言えるだろう……。」
宮坂誠「えーっと……それは柊が思う運命とは違うもの、なんだよな……。」
柊「ああ……しかし、同じでもある……。僕が認識し、操作する世界もまた……人間による意味付けを基にしている……。」

宮坂誠「はあ……。」
柊「……問題は、その物語をどのように作るか。物語の方向を決めるのは、語り部の”思い”――強い”願い”だ。意思なしに、運命を意味付けることはできない……。」
柊はコーヒーの水面に視線を落としている。

視線を落としていても、その目は何か途方もないものを視ているようだ。
柊「君は、運命を感じるとして――何を願う?」
宮坂誠「俺……?」
柊「そう、君だ……君の運命に意味を見出すのならば、君自身の願いを知らなければならない。」
宮坂誠「お、俺は願いなんてそんな……大げさなもの。」
柊「……いいや、大げさではない。言ったはずだ……世界を支配するかどうかも、君次第だと。」
願い――そんな風に考えたこともなかった。
毎日平凡に生きてて、ちょっとした目標とか、あれが欲しいなんて気持ちはあるけれど、
自分がどうしたいとか、しっかり向き合ったことがないように思う。
そして柊とのこれまでの時間の中で、浮かんでは消えていった思いがあったようにも感じる。
思い出せるだろうか……思い出せたとして、俺はそれをどういう風に受け止めればいいんだろう。
手に持ったコーヒーの表面に、蛍光灯の光がちらちら揺れている。
柊「さて――」
宮坂誠「え。あれ、いつの間に!?」
柊の声に顔を上げると、いつの間にか元の服に着替えた柊が立っている。
柊「乾いたようだったからな……勝手に拝借した。」
宮坂誠「まあ、いいんだけど……」
柊が立ち上がってたことにも気付かないなんて、どれだけ悩み込んでたんだろう。
いやしかし柊はたまにもの凄い存在感のなさを発揮する。今回はそうだったということにしとこう。
柊「世話になったな……そろそろお暇しよう。」
宮坂誠「え!あの、もう遅いし……泊まってっても……」
柊「遠慮する。」
いつになくばっさりフラれてしまって、がっくりと肩を落としてしまう。なんか想像以上にショックだ。
柊「君も落ち着かないだろう……。」
フォローのつもりなんだろうか。遠慮の理由がうなだれる頭の上から降ってくる。
凹んでる気持ちに気づかれている恥ずかしさ半分、気遣われる嬉しさ半分という気持ちで、
とりあえず玄関まで見送ることにした。
宮坂誠「今日はなんか、その……巻き込んでごめん。」
柊「問題ない……。よく考えて、君の答えを出すといい。」
宮坂誠「え?」
柊「願い、について。」
宮坂誠「……。」
柊「それこそが、君の運命を決めるだろう……。」
宮坂誠「……柊は、どんな願いを?」
柊「……秘密だ。また、明日。」
去り際に視線だけをこちらに向けながら、柊はそう言って俺の家を後にした。
残された俺は、玄関の前で柊の去っていった方をぼんやりと眺めながら、彼の言葉を咀嚼している。
宮坂誠「また明日……また明日、か……。」
その言葉に胸が躍る理由を、そろそろ自覚しないといけないのかもしれない。
体験版はここまでです!続きは完成版でお楽しみください。
2025/11/29 「世界はきみのためにある4」にて頒布されたギノ酸のWeb公開ページです。
愛について。
クロスフォリオで読みたい方はこっち→クロスフォリオ公開ページ
虚像の続きです→虚像 ※こっちはR-18
↓サムネを押すとPDFプレビューが開くよ

2025/11/29 「世界はきみのためにある4」にて頒布された長谷酸のWeb公開ページです。
余生でやるラブコメ。
クロスフォリオで読みたい方はこっち→クロスフォリオ公開ページ
↓サムネを押すとPDFプレビューが開くよ




参さんの作品の三次創作のおまけです → あいのう

2024/8/24 上遠野作品Webオンリー『世界はきみのためにある2』にて発行
アンソロ『Quiet hour』より再掲
参さんの作品の三次創作です→ 身から出た錆
猫なで声。
猫をかぶる。
猫も木から落ちる。……これは違う。
それらはなんでもない慣用句であり、日常会話で流される程度の意味合いしかない。少し前までは。
自分には動物を愛でる趣味はなく、猫という生き物への解像度も最低限あればよかった。全身に毛が生え、概ね似たような形状をしており、世界各地で愛玩動物として人気のある生き物。それが猫。
しかし、ひょんなことから猫に関する知識を一夜漬けもかくやとばかりに短時間で詰め込み、そしてそのまま知識が定着してしまった。おそらくその辺の一般人や、実際に飼育している者の平均値よりも詳しくなってしまった。
自分もなかなか健気なもので、知識を得た対象はその他大勢より特別な視点が交じる。事実と比較しての正誤確認、新しく得た知識と結びつけることによる納得、単に目に入りやすくなってる、云々。
正直、うんざりではある。
猫が世間的にどう思われていようと、自分の仕事にはなんの支障もない。正誤を判断する必要などまったく存在せず、故にそんなことを考えるリソースが無駄極まる。
知る必要のないことを知ったところで、自分には選ぶ資格があると思い上がるだけだ。
(記憶も好きに消せれば便利なんだが……)
記憶操作の能力を持つ構成員のデータをいくつか思い浮かべる。こんな私的なことに流用できるわけもない。第一本人了承の上で記憶を弄らせるほど信用のおける者などいない。
こんな思考は無意味だ。
「みゃあ」
淀んだ空気を転がして遊ぶような、あどけない鳴き声がひとつ。散漫な思考を持て余しながら動かしていた足をぴたりと止める。次の任務に向かう道中の、人気のない小ぢんまりした通りまで来ていたようだ。考えずとも勝手に足が向かうとは、なんとも便利な身体だ。
鳴き声の主は特に探すまでもなく、左手側に位置する店の前でただ座っているだけだった。こちらに顔を向けている様からも、先程のひと鳴きは呼びかけの意を含んでいるのだろう。その瞳にも姿勢にも警戒心はない。首に嵌ったアクセサリーが、人馴れした性質の根拠を示している。
見るからに成猫であり、身体はやや大きめといったところか。整った毛並みから、いい生活をしているだろうことも想像に難くない。そんなことはどうでもいいのだが――全身を覆う毛色に比べれば。
「……ロキ」
否が応にも頭に残っているその名前を口にすれば、茶と黒で汚れたサビ柄の猫は、再び「にゃあ」と鳴いた。間違いなく返事をしている。噂だけはかねがね、悪戯とフライドチキンが好きで、予防接種が嫌いな、あの。
(捕まえた方がいいのか?)
今は捕獲要請など上がっていない。それでも、もしかしたら……手のかかるこの猫を、一番乗りで捕獲して、そして、
(いや、違う、何を考えている)
眉間により一層集まったシワを、何も知らない猫が黙って見つめている。こいつは猫のくせに敵意もなく人間の顔を見つめているな。本当に何も知らない猫だろうか?
目を閉じ、ため息ともつかないひと呼吸を落として、猫の横を通り過ぎようと――した。
「……奇遇だな」
任務の関係上、いかなる状況であっても他者の気配を感知することは怠らない。そのはずだが、目の前の彼を前にしては、鋭敏を自負している感覚も意味を為さなくなる。彼を認識してはじめて、店を出た合図であろうドアベルの音が鼓膜を揺らす。自分と猫以外存在しなかったはずの通りに、なんの前触れもなく現れたのだ。
ちょうど猫が鎮座していた店に彼は入っていたらしい。この調子では店員も入退店に気づいていない可能性がある。自分より幾分低い位置から長い前髪の間の瞳が覗く。その顔には驚きも感嘆も見当たらない。いつも通りの無色透明である。
「……これは、まさか。お会いできるとは。お買い物ですか?」
驚きはしたが、この方に会って驚かなかったことは数えるほどしかないために、すっかり慣れたものだ。動悸を無理矢理にでも押さえつけて、平常の血圧で無難な答えを返す。誤魔化せているとは思えないが。
「まあ、そんなところだ……」
感情の籠もらない質問に、体温のない返答が返り、通りには沈黙が落ちる。こういうときには猫は鳴かないのか。所在なく猫に視線を移したところで、興味がなさそうにそっぽを向いてあくびなどしているときた。
彼がこちらに何かを尋ねるのは非常に稀だ。今だって、何をしにどこに向かうのかも聞くそぶりはない。興味がないというよりは、すべてお見通しなのだろう。いや、すべてをお見通しならば、すべてに興味がないと等価ではないか?
「よく、ロキがわかったな……会ったことはなかっただろう?」
どこにも向かわない沈黙を導いたのは、彼の意外な質問だった。いつの間にか彼の腕にはサビ色の毛玉が大人しく抱かれている。考えた矢先からさっそく質問をされてしまったわけだが、思考をすべて読まれている(推定)のに尋ねる意図とはなんだ?そもそも、何を応えるべきだ?
彼の顔を窺い見ても、答えは書かれていない。興味があるとは書いていないが、興味がないとも書いていないのだ。
「いえ、その……特徴は存じていましたので、当てずっぽうで、声をかけてみただけでして……」
散々迷って結局、嘘ではないが詳細な真実でもない中途半端な言葉になる。当てずっぽうの中には妙に確信めいたものが存在したのだが、そんなことを語っても冗長なだけだ。
彼は一度も変わっていない表情のままじっと見つめ返してくる。こちらを知っていると同時に、世界のあらゆることを知っている故の、ごく平坦な関心。
「……」
ゆるく、その目が細められる。咎めているような、呆れているような、そのどれでもない、ただ意味のない筋肉の反応であるような。
「……慎重が停滞を招いている。自身の望みに気づかなければ、打開する術はないだろう……」
ボソボソと、聞き取りにくいはずなのに妙に耳に残る声が隙間風となって鼓膜に届く。仰々しい物言いとは裏腹に、自分の脳内には、ビルのモニターから聞こえてきた『ガードばかりで進展しないかも……時には大胆なアタックで振り向かせよう!』という脳天気な占いのナレーションが響いている。非常に無礼な脳内変換だ。
どうかしている。アタックしたその先には何もない。
ふう。ほんの小さなため息をついた彼が、いつもより出番の多い口を開く。
「僕は……この店によく来ている。取り扱う品が、どれも興味深い因果を持っている……それに、ロキも気に入ったようでな」
脈絡なく言葉が紡がれている。尋ねていない上に、正直に言えば興味があるわけでもない情報。それでも、もうこの店を、通りを、似たような景色を見ただけで思い出してしまうだろう。
やれやれ、という表情の彼が視線を寄越す。『次は君の番だ』と言っている。お手本を真似してやってみなさい、と。
相手に知らせて、記憶に刻みつけて、そうしてアタックした先には、目の前のそれと同じしてやったりの顔があればいいのかもしれない。
彼の中に存在を焼き付けるに足らずとも、その一片だけでも、
「にゃお」
腕の中に収まっている猫がこちらを向いて鳴く。
「ああ……ロキに君から貰った餌の話をしたからな……。覚えてしまったんだろう」
慣れない一歩を踏み出しかけた膝から力が抜けそうになる。すでに彼の中には自分に関する特筆すべき記憶があった。結局猫をどうにかこうにかすればいいのか。身も蓋もない。
脱力がなぜか怒りに転じて、呑気に毛を繕う猫への対抗心に変わる。これを介さずとも記憶に残すことなどいくらでもできるのだ。猫に語っても意味のない間抜けな果し状を脳内で叩きつけ、
「あの、私は――」
意味のない、間抜けな、自分を語って聞かせる。
「あれ、困ったおじさんじゃん」
「……ああ、君か。その節はどうも」
見覚えのある子どもが、川沿いの階段に腰掛ける私の隣に無遠慮に座る。かつて見かけた格好から幾分か厚着になっている姿は時間の経過を感じさせる。
「猫見つかったの? よかったね」
私が語っていない過去の猫探しの結末を、なんの躊躇いもなしに言い当てる。別にこの子どもに超能力があるとか、特別に敏いとか、統和機構を狙って日夜情報収集をする反組織のエージェントとかそういう話ではない。――いるのだ、私の足元に、件の猫が。
「お陰様で」
「役に立ったでしょ、ミョンプチ」
「まあ、なんやかんやで役に立ったような気がするよ」
「めっちゃ適当じゃん」
子どもは大人しく佇む猫を撫でている。さすが野良猫を集めていただけあって扱いがうまく、猫も逃げずに喉を鳴らすばかりである。
「おじさん、猫に好かれるようになったんだ」
「好いてるわけじゃない、餌を出す人間と認識されただけ」
「ツゴーの良い男ってやつだ」
「そうだろうな」
猫からどう思われていようとどうでもいい。ただ見かけるたびに寄ってくるようになったのは少々面倒だ。しばらくしたら飽きて帰るのだが。
「この猫おじさんのじゃないんだよね?」
「そうだよ」
「なんで外にいんの? 危なくない?」
「さあ、それはなんとも」
気のない返事をしたはいいが、家猫は基本的に完全室内飼いが推奨されるという知識はある。地方ではまだ外と内を自由に行き来する飼い猫も存在するが、都心ではそうそう見ない光景だろう。
猫への愛着はない上、自分もそしてあの方も世間体を気にする性分でもないだろうことから、あの方が良いのなら特に何か進言することもない。
しかし、だ。
この猫はおそらく、あの方が特定の住居を持たない故に外に出されている。ならば、一応この近辺に拠点を構えている自分が室内飼いにすると助言してはどうか?
今はこれで満足しているように見えるあの方も、本当は室内飼いにしたいと考えているかもしれない。私がそのニーズを満たすことができれば、あの方にとって替えの利かない役割を担うこととなる上、猫目当てに会う頻度も増えるかもしれない。
「おじさん猫好きになった?」
「全然。ビジネスライクな関係だ」
「猫とビジネスすんの?」
「強欲を呼び起こす忌々しい悪魔でもある」
「悪化してんじゃん」
睨んでもどこ吹く風の脳天気な毛玉に屈するわけにはいかないので、先程浮かんだ案は却下となった。
2024/8/24 上遠野作品Webオンリー『世界はきみのためにある2』にて発行
アンソロ『Quiet hour』より再掲